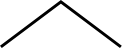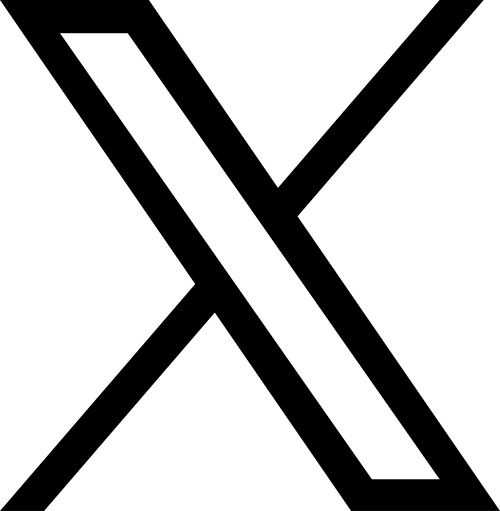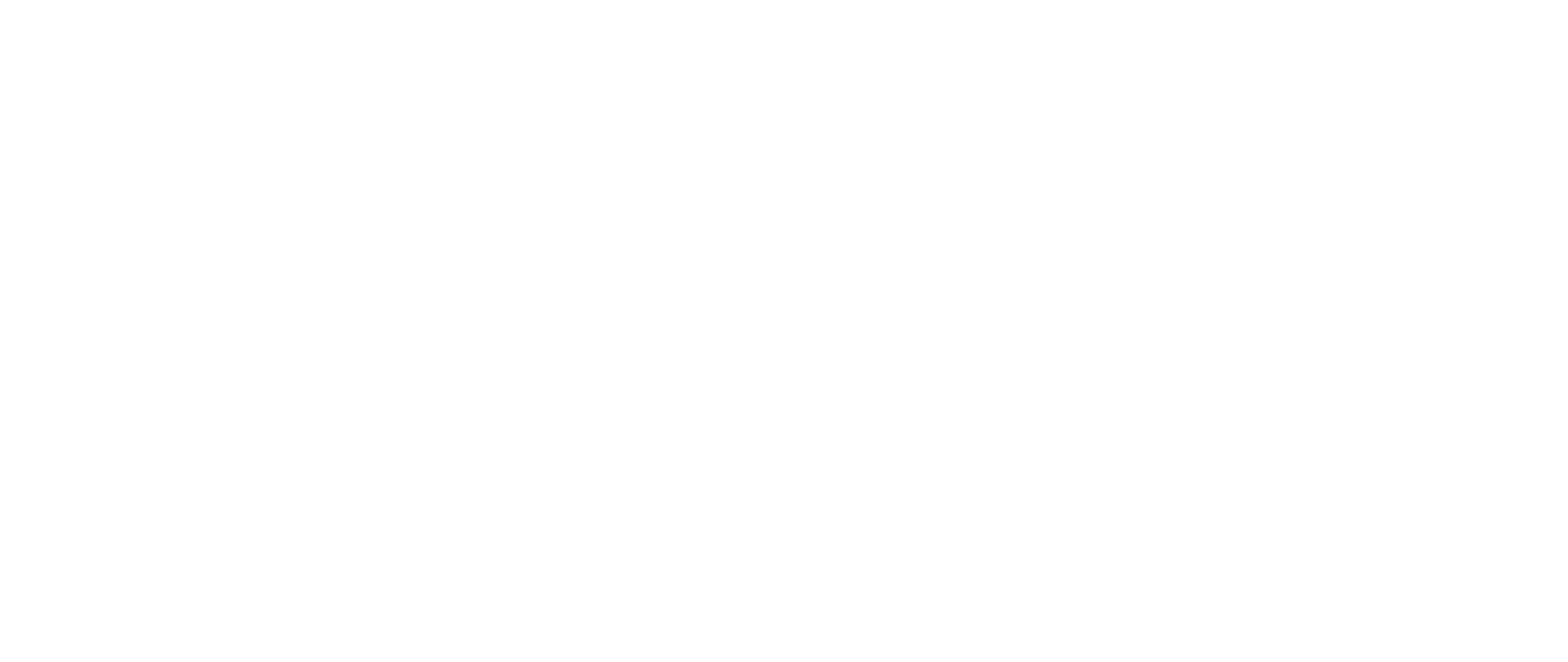【2025年版】初心者にもおすすめ!リコー・オリンパス・キヤノンなど全10社のコンパクトフィルムカメラ厳選紹介
「フィルムカメラに興味はあるけれど、何を選べばいいのか分からない」
そんなあなたに向けて、リコー・オリンパス・キヤノンなど、全10社の初心者でも扱いやすく、持ち運びにも便利なコンパクトフィルムカメラ。
見た目も可愛らしく、日常をさっと切り取るのにもぴったりです。
本記事では、カメラごとの特徴や実際の作例もあわせて紹介していますので、ぜひお気に入りの一台を見つけてみてください。
目次
コンパクトフィルムカメラとは?
一眼レフのフィルムカメラに比べて、軽量かつコンパクトなフィルムカメラの総称です。そのサイズ感は種類によってさまざまですが、手に収まるタイプのモデルが多く見られます。
「軽量でコンパクト」で人気の「写ルンです」は、撮影を終えると本体ごと交換する必要がありますが、コンパクトフィルムカメラは本体はそのままに、フィルムを交換するだけでいいので、何度も繰り返し使うことができます。
コンパクトフィルムカメラの魅力
1. 小型で軽量であること
一眼レフカメラでの撮影においてネックとなるのは、その重さ。カメラと交換レンズをカバンに詰めたけど、取り出すのがおっくうで思ったほど写真が撮れなかった…ということはありませんか?レンズが一体型のコンパクトフィルムカメラなら、カメラを持ち出すだけでお出かけの準備は完了。かさばることなくカバンに忍ばせておけるサイズ感が魅力です。
2.操作が簡単であること
カメラごとに搭載されている機能はさまざまですが、基本的にシャッターボタンを押すだけで撮影できます。フィルム交換さえすれば、誰でも手軽にフィルム写真を楽しむことができるので、初心者でもおすすめ。ふとした瞬間にサッと撮影できる機動力があるので、一瞬を逃したくないスナップ撮影やお子さんの写真を撮影するのにもぴったりです。
ここからは、連載「わたしのカメラ」で紹介したカメラの中から、メーカーごとにおすすめのコンパクトフィルムカメラを紹介します。
キヤノン(Canon)
連載「わたしのカメラ」においても、人気の高いキヤノンのフィルムカメラ。キヤノンは、1934年に国産初の35mmレンジファインダーカメラの試作機「KWANON(カンノン)」を試作して以来、2000年代までフィルムカメラを製造していたことで知られる歴史あるメーカーです。レンズが交換できる一眼レフタイプも根強いファンがいる一方で、近年人気があるのはコンパクトカメラの「オートボーイ」シリーズ。
シンプルな操作性でシャッターチャンスを逃さないシンプルな操作性と、コンパクトカメラながら、侮れないボケ感、優しく温かな描写が特徴です。
機種ごとに、実際の作例を見てみましょう。
1. Autoboy Luna105

38-105mmの2.8倍ズームレンズを搭載したオートフォーカス35mm全自動ズームコンパクトカメラ。人工知能オートフォーカス搭載で被写体に合わせて自動で最適なピント位置を選択。動きのあるシーンでもピントが合いやすいため、初心者でも失敗が少なく、安心して撮影を楽しむことができます。
幅・高さ・奥行:123x64x50mm
重量:約255g
Autoboy Luna105の特徴
オートフォーカスのおかげで、ピントを合わせる手間がないため、心が動いた瞬間にシャッターを押せるのが、このカメラの魅力。そのときの心の温度を、そのまま写真に残せるような感覚が嬉しくて、撮ることがとても好きになりました。一方で、ピントがどこに合っているかがわからないため、現像した写真の写りが完璧ではないときもよくあります。でもそれもこのカメラの“個性”と捉えて、現像を待つ時間も含めて楽しんでいます。
フィルムカメラに興味を持ち始めた人やカメラ初心者の方にはもちろん、すでに他のフィルムカメラを使っている方にもおすすめしたい一台です。コンパクトでありながらフィルム特有の写りやを感じられるので、フィルムの楽しさを改めて教えてくれると思います。
https://encounter.curbon.jp/gallery/mycamera-canon-autoboy-luna-105/
Autoboy Luna105の作例


2. Canon Autoboy ZOOM Super
1988年に登場した「Autoboy Zoom」は、Canonが初めてズームレンズを搭載したオートフォーカス・コンパクト機。レンズは35〜70mmのズームレンズで、当時としては十分な汎用性を備えています。赤外線を使ったアクティブ方式のオートフォーカスにより、ピント合わせも比較的スムーズ。操作系はとてもシンプルで、フラッシュの自動発光、フィルムの自動巻き上げ・巻き戻しと、まさに“誰でも撮れる”フィルムカメラの代表格といえるモデルです。また、1989年に発売された「Canon Autoboy ZOOM Super」は、レンズシャッター式AF35mm 全自動カメラとして、最高級機。現在でもその人気は絶えることなく、中古市場でも注目を浴び続けています。
幅・高さ・奥行:153×93×68mm
重量:640g(電池含む)
Canon Autoboy ZOOM Superの特徴
カメラを始めて1〜2ヶ月程経ち、ストロボ付きでポケットに入る、コンパクトなカメラが欲しくなり探していたところ、カメラのキタムラのジャンクコーナーで出会いました。
当初の予定とは異なり大きなサイズにはなってしまったものの、ズーム機能や歪で個性的な形に一目惚れし、すぐ購入を決めました。リモコン不良のジャンク品ということもあり安価でしたが、その他は問題なく機能しており、現在も元気に動作しています。
https://encounter.curbon.jp/gallery/canon-autoboy-zoom-super/
Canon Autoboy ZOOM Superの作例


3. Canon Autoboy S Ⅱ

1996年に発売されたAF35mm全自動ズームカメラ「Canon Autoboy S Ⅱ」。1993年に発売された、全自動ズームカメラの最高級機種「Canon Autoboy S(スーパー)」の発展型後継機として開発された。
「Canon Autoboy S」の高性能・多機能性を引き継ぎながら、ズーム比3.6倍の高倍率・高画質の38-135mmズームレンズを搭載。 コンパクトカメラでありながらも望遠・ボケまで楽しめる一台です。 また、ベストショットダイアルで、自動撮影から夜景・ポートレートなど7段階のモードを切り替えることができ、日付やキャプションを写し込める遊び心も健在です。
幅・高さ・奥行:133mm×70mm×65mm
重量:375g(電池含む)
Canon Autoboy S Ⅱの特徴
「露出もピントも巻き上げも自動のカメラを使ってみたい」と思っているときに出会いました。人間の目でも見えてるようで見えてない瞬間、フレームとフレームの間のような瞬間を撮れるところがとても気に入っています。音がなくなるような世界を写真にしたいときや、動きのあるものを追いかける時によく使っています。
https://encounter.curbon.jp/gallery/mycamera-canon-autoboy-s2/
Canon Autoboy S Ⅱの作例


4. Canon Autoboy 155

35mmAFコンパクトフィルムカメラ「Autoboy」シリーズの最上位機種として2002年に登場したCanon Autoboy 155。 小型・軽量・薄型でありながら、37-155mmの高性能4.2倍ズームレンズを搭載。
自動撮影から夜景・ポートレートなど7段階のモードを切り替えることができるベストショットダイアルや日付・キャプションの写し込み機能も健在。 一部外観にアルミを使用し、グリップ部分にグリーンのアクセントを施し、高級感を演出した外観デザインに。気軽に、かつ幅広くフィルム撮影を始めたい人には最適な一台です。
幅・高さ・奥行:112.0mm×59.5mm×48.3mm
重量:225g(電池別)
Canon Autoboy 155の特徴
私が「Canon Autoboy 155」を使うときは、美しさや画角、距離感はあまり気にせずに、その一瞬を感じたまま素直にシャッターを切ることがほとんどです。ピントがずれても味わい深いですし、思い出は、ぼやけるくらいが丁度いい。このカメラを使うようになってから、気持ちを込めた写真のよさを実感しました。心がときめく気持ちをそのままにシャッターを切ると、そのときの声や匂い、空気まで感じ取れる、温もりのある写真を撮ることができます。日々の光景をこのカメラとともに、心のままに記録し続けていきます。
https://encounter.curbon.jp/camera/mycamera-canon-autoboy-155/
Canon Autoboy S Ⅱの作例


5. Canon Autoboy MINI T

「Canon Autoboy MINI T」は、1991年に発売された35mmAFコンパクトフィルムカメラです。幅53mm・255gと、コンパクトフィルムカメラの中でも薄型・軽量なのが特徴。 同時期に発売された「Autoboy MINI」との違いは、 前作の「Autoboy TELE」の機能を引き継ぎ、カメラ前面のスイッチで38mm単焦点と70mm望遠の2焦点切り替えができる点。 前面に、電源スイッチ・2焦点切り替えスイッチ、上面には、セルフタイマー・シャッターボタン、背面には、日付設定ボタン・フラッシュ切り替えスイッチ、と極めてシンプルな操作性とデザインで、日常的に持ち歩けるシティなフィルムカメラです。
幅・高さ・奥行:125mm×68mm×53mm
重量:255g(電池含む)
Canon Autoboy MINI Tの特徴
軽くて持ち運びやすく、旅行や遊びに行くときにはいつも一緒!ポケットからパッと取り出して撮影できるため、何気ない一瞬を撮ることに適しています。持ち運びやすいカメラを使う理由は、写真を撮りに行く日は一眼レフも持っていきますが、ポケットサイズのカメラがあると「撮りたい!」と思った瞬間をフィルムに収められるから。買い物途中に出会った近所の猫や仕事帰りの夕焼けなど
生活のなかでも撮りたい瞬間と出会うので、カメラを取りだしてオート撮影ができるのはありがたく
Canon Autoboy MINI Tのような、すぐに撮影できるカメラは重宝しています。ときには玉ボケが出ることもあるので「一眼レフで撮ったっけ?」と思うことも。デジタルの一眼レフを使用するときも単焦点のオールドレンズを使用していますが、背景がソフトにボケるので柔らかい雰囲気の写真になります。フラッシュを焚くとパッキリした写りになりがちですが、ISO400以上のフィルムを入れて撮影すれば、少し暗い場所でもフラッシュを焚かずに撮れるところがお気に入りです。暖かく、柔らかい写真を撮りたい方におすすめのフィルムカメラです。このカメラで撮る夕焼けがだいすきです。
Canon Autoboy MINI Tの作例


6. Canon Autoboy D5

「Canon Autoboy D5」は、Canonのオートフォーカスコンパクトカメラシリーズ「Autoboy」の水陸両用の全自動35mm防水カメラとして、1994年に発売されました。 発売当時、世界最小・最軽量であったほどのコンパクトさ、そして可愛らしいデザインが特徴的。 陸上では、3点測距によるオートフォーカスが作動し、0.45m〜無限大まで、水中では水深5mまで撮影可能です。また、固定焦点撮影では1〜3m、マクロ撮影モードでは0.45m〜1mで撮影できます。 そして、陸上だけでなく、水中メガネやスキーのゴーグル装着時にも見やすい光学系、アルバダ式のファインダーが搭載。 カメラ底面のスイッチで、「35mm画面」と「パノラマ画面」を切り替えられる機能も搭載しています。 山・川・海・雪、あらゆるアウトドアシーンに対応した「冒険オートボーイ」という名に相応しい一台。
幅・高さ・奥行:133mm×88mm×56mm
重量:335g(電池含む)
Canon Autoboy D5の特徴
防水カメラなので、夏は川や海、冬は雪がある場所へも安心して持って行って撮影できます!
さらに、日付が入れられ、私が持っている他のカメラより広角なので重宝しています。おもちゃみたいなポップで可愛いフォルムで、優しい写りをしてくれて、お気に入りカメラの1つです!https://encounter.curbon.jp/camera/mycamera-canon-autoboy-d5/
Canon Autoboy D5の作例


7. Canon Autoboy S XL

「Canon Autoboy S XL」は、1999年に発売された35mm AFコンパクトフィルムカメラです。1993年に登場した「Canon Autoboy S」をベースに、上品なホワイトゴールドのボディに刷新されたカラーバリエーションモデル。特徴は、38–115mm F3.6–8.5の3倍ズームレンズ。コンパクトでありながら、望遠やボケ表現まで楽しめる一台です。1/1200秒の高速シャッターを搭載しており、一瞬のシャッターチャンスも逃しません。さらに「ベストショットダイヤル」によって、夜景やポートレートなど7種類の撮影モードをワンタッチで切り替え可能。日付や10種類のキャプションを写真に写し込める遊び心も魅力。機能性とデザイン性を兼ね備えた、頼もしい相棒です。
幅・高さ・奥行:130.0mm×70.0mm×59.8mm
重量:320g(電池別)
Canon Autoboy S XLの特徴
「Canon Autoboy S XL」で撮ったフィルムが初めて返ってきたときは、「この小ささでこんなに写るの?」と、とても驚きました。インスタントカメラだと写りがチープ過ぎるけど、フィルム一眼だとはっきり写り過ぎてしまう…と思う時に、よく使います。撮影時はデジタル・フィルムを問わず、さまざまなカメラを持っていきますが、一番気に入ったものは「Canon Autoboy S XL」で撮った写真だったなんてことも。もし壊れたとしても、すぐ買い替えたいくらいお気に入りのカメラです。ズームしたときのフォルムがなんとも特徴的ですが、それはご愛嬌。
https://encounter.curbon.jp/camera/mycamera-canon-autoboy-sxl/
Canon Autoboy S XLの作例


オリンパス(OLYMPUS)
OLYMPUSを語るうえで欠かせないのが、1960年代に登場したハーフサイズカメラ「ペンシリーズ」です。なかでも特に有名なのが「PEN FT」や「PEN EE3」といったモデル。いずれもコンパクトながら高性能を誇り、多彩なレンズやアクセサリーのバリエーションによって多くの注目を集めました。
このシリーズは、小型・軽量設計で持ち運びがしやすく、日常使いにも適しています。また、オリンパス独自のレンズブランド「ズイコ(ZUIKO)」は、コンパクトでありながら高画質を実現しており、写真表現においても妥協がありません。さらに、持っているだけで気分が上がるような、暮らしに自然と溶け込むデザインも魅力のひとつです。
機種ごとに、実際の作例を見てみましょう。
1. OLYMPUS PEN D

1962年に発売された「OLYMPUS PEN D」は、コンパクトなボディーにF-zuiko F1.9 32mmの大口径レンズ、高速1/500秒シャッター、LV値直読式内蔵露出計などを詰め込んだ、まさに「プロ仕様のペン」。F1.9からF16、1/30秒から1/500秒まで設定できるこのカメラは、さまざまなシーンや光の条件をカバーします。
幅・高さ・奥行:108mm×67mm×50mm
重量:400g
OLYMPUS PEN Dの特徴
ハーフカメラとは思えない描写力と、独特な光の捉え方がこのカメラの魅力です。それによって最近は、光や輝きを意識した写真を撮ることが増えてきました。また、気軽に持ち歩けるサイズ感で、日常の中の「残したい瞬間」を自然に切り取ることができます。一台だけ持って散歩に出かけることも多く、今では身近な相棒のような存在です。不便さを楽しめる人や、既存のカメラに物足りなさを感じている人には、特におすすめ。現像したとき、想像以上の写りに驚かされるはずです。
https://encounter.curbon.jp/gallery/mycamera-olympus-pen-d-2/
OLYMPUS PEN Dの作例


2. OLYMPUS PEN EE

1961年にオリンパスが発売したハーフカメラ「OLYMPUS PEN EE」。固定焦点や自動露出、シャッタースピード固定によるシンプルな操作性が特徴です。ボタンを押すだけで、誰でも簡単に美しい写真が撮れるカメラとして人気を博し、ペンシリーズが広く普及するきっかけとなりました。
幅・高さ・奥行:108mm×66mm×42mm
重量:350g
OLYMPUS PEN EEの特徴
友達や家族のありのままの表情を撮影するときは、ピントを合わせる時間すらも惜しいもの。だからこそ、片手でカシャッと今を切り取れるこのカメラは、私にとって欠かせない存在です。複雑な操作が苦手な人や、たくさんの思い出を残したい人におすすめしたい一台です。
https://encounter.curbon.jp/gallery/mycamera-olympus-pen-ee/
OLYMPUS PEN EEの作例


3. OLYMPUS PEN EE-3
1973年に発売された「OLYMPUS PEN EE-3」は、1961年から続くEEシリーズの第3世代モデルです。ペンシリーズの中でも長く支持されたロングセラー機となっています。
EE-3では、「GN14専用フラッシュマチック機構」が搭載され、専用ストロボ「PS 200」と連動して被写体までの距離に合わせて自動で絞りを調整。これにより、室内や逆光など光量の難しい環境でも安定した撮影が可能です。また、光量不足時にはファインダー内に「赤ベロ」と呼ばれる警告が表示され、シャッターが切れない仕組みになっているため、失敗写真を防げます。1986年まで製造されたため中古市場にも状態の良い個体が多く、ハーフサイズカメラの入門機としておすすめです。
幅・高さ・奥行:108mm×66mm×47mm
重量:335g
OLYMPUS PEN EE-3の特徴
最短焦点距離が0.9mと、似たような使用感である写ルンですと比較してもピントの合い始める位置が遠いため、油断するとカメラから近い被写体がボケやすいです。でも、こうした像の荒さが思い出をより思い出らしくする効果があるように思います。オリンパスの銘玉であるズイコーレンズの描写力に驚かされる場面も少なくありません。苦手とされている暗所での撮影も、きちんと光源の位置などを把握しながら撮影すれば思いのほか豊かな描写を残してくれます。
カメラのサイズや操作の簡便さからも、常に持ち歩いていても邪魔になることがなく、まさに日常が思い出に昇華するカメラと言えるでしょう。フィルム価格の高騰が、いよいよ手のつけられない水準へと達してしまったとすら思える、ここ1年ほどの状況。そんななかでも中古相場での手の出しやすさや、通常の倍の枚数撮影できるハーフカメラである点からも、いま最もおすすめしたいカメラだと思っています。
https://encounter.curbon.jp/gallery/mycamera-olympus-pen-ee3/
OLYMPUS PEN EE-3の作例


4. OLYMPUS PEN EES-2

「OLYMPUS PEN EES-2」は、1968年に発売された「OLYMPUS PEN EE」シリーズの決定版となるハーフサイズレンズシャッターカメラ。1960年代から1970年代にかけてのハーフフィルムカメラブームを牽引した代表的なモデルの一つで、世界初のプログラムEEシャッターを搭載。これにより露出調整が自動化され、ピントを合わせるだけで簡単に撮影ができるため、フィルム入門機として高い人気を誇っています。また、単焦点レンズの「Dズイコー30mm F2.8」はハーフサイズながら高い解像度を実現しており、十分な写りの良さを備えています。初心者からフィルム愛好家まで幅広く支持される使いやすいカメラです。
幅・高さ・奥行:108mm×66mm×47mm
重量:370g
OLYMPUS PEN EES-2の特徴
とにかくコンパクトで、ハーフサイズということもあり罪悪感無く撮れるのが良いです。またシャッターと露出計もアナログなので、電池切れの心配もありません。フォーカスは目測で、なんとなくの距離を合わせます。最初はピンボケ写真を量産しましたが、使っているうちに慣れてきました。デジタルは綺麗に写り過ぎるので、フィルム特有の光線漏れやハレーション・古いレンズのにじみなど、デジタルでは補えないフィルム特有の表現が欲しいときに重宝しています。良い意味で写りすぎない、アナログな魅力が詰まったカメラだと思います。
https://encounter.curbon.jp/camera/mycamera-olympus-pen-ees-2/
OLYMPUS PEN EES-2の作例


5. OLYMPUS AF1
「OLYMPUS AF1」とは、1986年にオリンパスから発売された35mmフィルムカメラです。このカメラは、当時の最新技術を取り入れた、高精度のオートフォーカスシステム、高品質のレンズ、そして小型軽量なボディが特徴。また、プログラムオート露出機能を搭載しているため、被写体に合わせて最適な露出を自動的に設定してくれます。AF1には、多くのバージョンがありますが、最も有名なのはF2.8の明るいレンズと、より高精度なオートフォーカスシステムを搭載した「OLYMPUS AF-1 SUPER」。同機種は、美しいボディデザインと高い操作性を兼ね備えた、非常に人気のあるカメラです。
幅・高さ・奥行:117㎜ x 64㎜ x 47 ㎜
重量:250g
OLYMPUS AF1の特徴
約3年前、代官山にあるカメラ店で出会ったカメラが、私のお気に入りの一台です。「初めてフィルムカメラを購入する方には」と、お店の方に強くオススメされたのがOLYMPUS Af-1でした。このカメラはシャッターを押すだけで撮影ができる手軽さはもちろん、コンパクトな形状なので外出時にも持ち運びが容易です。他のカメラとは比較することができませんが、シャッターを切った後のフィルムが巻き取られる音は、私にとって非常に響き渡るもので、一枚一枚丁寧に撮影されていることが伝わってきます。また、オートフォーカスなのでズーム機能もなく、今目の前に広がる景色をそのまま写真に残してくれるため、よりリアルな印象を受けます。現像した写真を見返すと、その時の風景や思い出が鮮明に蘇ります。購入してから既に3年が経ちますが、このカメラを使い続ける理由は上述した理由に加え、これまでたくさんの景色を撮らせてくれたことへの感謝の気持ちがあります。今後も大切に使い続けたいと思います。
OLYMPUS AF1の作例


コニカ(Konica)
コニカは、日本の老舗カメラメーカーで、特に1970年代から1990年代にかけて多くのコンパクトフィルムカメラを製造していました。可愛らしくシンプルなデザインでありながら、オートフォーカス(AF)、自動露出(AE)、自動巻き上げなどの機能を備えた機種が多く、初心者に適したモデルがそろっています。
特にコニカ製のレンズ「ヘキサノン(HEXANON)」は、トップクラスの解像力と色再現性を誇り、シンプルながらもしっかりとした写りを実現。また、シャッター音やフィルムの巻き上げ音が静かなため、スナップ撮影や室内での撮影にも向いています。
機種ごとに、実際の作例を見てみましょう。
1. Konica RECORDE

1963年に発売されたえ「Konica RECORDER」は、半自動露光機能を搭載した35mmフィルムカメラ。その当時としては先進的な露光計システムを持つこの機種は、被写体の明るさを正確に計測し、露出を自動調整することが可能。また、操作が比較的シンプルでありながらも、高品質な写真を撮影することができることが特徴です。
スナップ写真からポートレートまで幅広い撮影シーンに対応し、当時のアマチュアからプロまで幅広い層に支持されました。そのため、現在でもコレクター間で人気があり、コニカのカメラの歴史において重要な位置を占めています。
寸法:幅112.5×高さ77×奥行30.5mm
重量:250g(電池別)
Konica RECORDEの特徴
カセットプレイヤーの様な、四角くてレトロで可愛いデザインが使いたくなるポイントです。
フィルムが縦に送られる構造なので、ハーフカメラですが、通常の35mmフィルムカメラと同様に、カメラを横位置で構えて横長の写真を撮影できる点が魅力です。さらに、データバック付きのモデルでは、写真に日付を記録でき、単3電池で動くのも嬉しいポイント。ISO感度を設定すれば、その他の設定はオートで行われるため、カメラボディをスライドしてシャッターを切るだけで撮影できる点が気に入っています。https://encounter.curbon.jp/gallery/mycamera-konica-recorder/
Konica RECORDEの作例


2. Konica 現場監督 28 HG

頑丈で屋外設置が可能な工事現場専用のカメラとして開発された「現場監督28HG」は、防水・防塵・耐衝撃性に優れ、大光量フラッシュを内蔵した広角レンズ付きのコンパクトカメラです。28mm F3.5のレンズを採用し、広範囲を撮影できるため、工事現場の空気感をそのまま写真に収めることが可能。10m先まで照射できる大型フラッシュを装備しており、暗所での撮影にも適しています。また、JIS C0920 保護等級7級(防浸型)の規格をクリアしており、水面下1mで30分間の耐水性も備えています。
寸法:幅142.5mm×高さ83.5mm×奥行57mm
重量:375g(電池含まず)
Konica 現場監督 28 HGの特徴
私が使っている「Konica 現場監督 28HG」は、大型ストロボが付いているため、暗いところでも被写体からある程度離れて撮影できるのが魅力。頑丈なうえに、写りもよく、露出はオートモードで気軽に撮影できます。このカメラと出会ってからは、スナップ写真を撮るようになりました。日常的にカメラを持ち歩きたい人や、カメラに詳しくないけど興味がある人におすすめしたいです。誰でも楽しく使えるカメラだと思います。
Konica 現場監督 28 HGの作例


3. KONICA C35

「KONICA C35」は、1968年に発売された日本初の35mmコンパクトカメラ。コンパクトなボディに高性能なコニカ製の38mm F2.8のレンズを搭載し、シャッター速度優先の自動露出(プログラムAE)機能を備えています。使いやすいシンプルな設計と、高いデザイン性は、初めてのフィルムカメラとしても最適です。
幅・高さ・奥行:112mm×70mm×51mm
重量:370g
KONICA C35の特徴
小さくて軽量、操作も簡単なので「これからフィルムカメラを始めたい」という方にオススメのコンパクトフィルムカメラです。時代を感じさせるクラシックなデザインは「フィルムカメラらしさ」を楽しめて、カバンに入れておくだけでもテンションを上げてくれるはず。ピント調整をするだけで撮影できるのにキレイに写る気軽さが気に入って、旅行やお散歩に出かけるときはよく連れ出しています。
KONICA C35の作例


ミノルタ(minolta)
ミノルタは、かつて世界的な人気を誇った日本のカメラメーカーです。多くのユーザーから高い評価を受けたブランドとして知られています。
特に注目すべきは、ミノルタ製のレンズ「ロッコール(Rokkor)」。柔らかさと繊細なシャープさが絶妙に調和した描写力は、ポートレートや風景撮影に最適な表現力です。自然な色合いと空気感を丁寧に写し取る描写は、多くの写真愛好家を魅了した魅力のひとつ。
また、価格帯や操作感、コンパクトなボディ設計により、初心者でも扱いやすいという特徴もあります。技術力の高さと親しみやすさを兼ね備えた、日本カメラの名作のひとつと言えるでしょう。
機種ごとに、実際の作例を見てみましょう。
1. minolta TC-1

1996年に発売された「minolta TC-1」は、ミノルタの代表レンズ「ロッコール」を搭載した高級コンパクトフィルムカメラ。圧倒的なコンパクトさと上品なチタンボディに、一眼レフ用レンズをも凌駕する超高性能レンズ「G-ROKKOR 28mm F3.5」を搭載していますオートフォーカスの性能も高いため、フィルム初心者も扱いやすいのがポイント。28mmと広角の為、屋外での撮影に適し、完全円形絞りが美しいボケを引き出します。
幅・高さ・奥行:99x59x29.5 mm
重量:185g(電池別)
minolta TC-1の特徴
小型・軽量なので、サブカメラとして使いやすいカメラですが、メインで持ってきたカメラよりもよく写ることも多いので、小さな見た目と描写のギャップが楽しめます。深みのある色合いで写るので、何気ない場面が作品のように仕上がります。
https://encounter.curbon.jp/camera/mycamera-minolta-tc-1/
minolta TC-1の作例


2. MINOLTA repo

1960年代に一世を風靡したハーフサイズカメラのブームの中で、1963年に登場したミノルタ初のハーフサイズカメラ「MINOLTA repo」。このカメラの特徴のひとつは、一般的なレバー式ではなくダイヤル式を採用した巻き上げ方式。カチカチとダイヤルを回す感覚は、まるで使い捨てカメラを操作しているかのような新鮮さが楽しめます。露出はセレン追針式露出計による手動プログラムで決定され、操作ダイヤルは距離とEV値のみ。絞りとシャッター速度は固定ですが、バルブ以下のフラッシュマークの位置にダイヤルを回すと、シャッター速度が1/30に固定され、絞りを個別に設定できます。
搭載レンズは「ROKKOR 30mm/F2.8」の3群4枚テッサー型で、ハーフサイズながら優れた発色を誇ります。カメラの色はブラックとシルバーの2種類があり、特にブラックは生産台数が少ない希少モデルです。
幅・高さ・奥行:107mm×66mm×46mm
重量:約400g
MINOLTA repoの特徴
「MINOLTA repo」と出会ったのはなんとフリマアプリ。2000円という破格で手に入れたジャンク品です。
コンパクトなサイズで持ち運びに便利なところ、見た目が可愛らしいところ、ハーフカメラなので通常の倍の枚数撮影できるところが気に入っているポイントです。他のカメラにはない、特徴的な写りもこのカメラが好きな理由のひとつ。露出やピントの加減が難しく、光や色味の出方にも癖があるカメラだと思います。でも、時折思いがけない良い写真が撮れることがあるのが、このカメラのいいところ。他のカメラ以上に、現像するまで仕上がりがわからないワクワク感にハマっています。
MINOLTA repoの作例


リコー(RICOH)
リコーは、日本を代表する老舗の精密機器メーカーであり、長年にわたって革新的なカメラを世に送り出してきたブランドです。1950年代からフィルムカメラ市場に本格参入し、コンパクトながらも高性能なモデルを数多く手がけてきました。特に、スナップやストリートフォトに適した設計が多くのフォトグラファーから高い評価を受けています。
リコーのカメラは、手のひらに収まるほどのサイズ感でありながら、高性能な描写力を備えているのが特長です。ストリートやスナップ写真に特化した設計は、決定的な瞬間を逃さず切り取るための頼もしい相棒。加えて、シンプルな操作性で初心者でも扱いやすく、プロのサブ機としても信頼される存在です。
使うほどに手に馴染む実用性と、写真に集中できる軽快さは、まさに撮ることそのものを楽しませてくれます。
1. RICOH AUTOHALF SE2

「RICOH AUTOHALF SE2」は、1976年に発売されたハーフサイズのフィルムカメラです。1962年から展開された「AUTOHALF」シリーズの一つで、前機種である「RICOH AUTOHALF SE」に改良を加えたモデルとなっています。セルフタイマーや自動巻き上げ機能を備えつつ、新たに外付けのフラッシュが装着できるアクセサリーシューも追加されました。
このカメラの特徴は、電池を使わずに撮影ができること。レンズのまわりに搭載されたセレンが、太陽光を利用して露出を自動で調整します。また、カメラ下部のダイヤルを手で巻いておくことで、フィルムが自動的に送られる仕組みです。ピントは約2.5メートルに固定されていますが、操作がとてもシンプルなので、フィルムカメラ初心者でも安心して使えます。コンパクトでかわいらしい見た目と、気軽に楽しめる機能性。手軽に始める一台としておすすめのフィルムカメラです。
幅・高さ・奥行:89.0mm×67.0mm×34.5mm
重量:350g
RICOH AUTOHALF SE2の特徴
今までたくさんのハーフカメラを使ってきましたが、特にお気に入りのカメラが「RICOH AUTOHALF SE2」です。他のメーカーと比較すると、RICOHのレンズは発色が良いと個人的に感じています。また、「RICOH AUTOHALF SE2」の特徴は、フィルムの巻き上げがレバーではなくゼンマイのパワーで自動に行われる点です。事前に巻いておいたゼンマイがフィルムの巻き上げを行ってくれるので、手動巻き上げのフィルムカメラではなかなか行えない連写が可能となります。これは、2枚1組の写真を撮れるハーフカメラにとって、とても魅力的です。さらに、ポケットに入るくらい小さく、気軽に持ち歩いて撮りたい瞬間にそのままサッとシャッターを切ることができます。日常使いにとても便利なカメラです。
https://encounter.curbon.jp/camera/mycamera-ricoh-autohalf-se2/
RICOH AUTOHALF SE2の作例


コンタックス(CONTAX)
コンタックスは、ドイツのカメラメーカーであるカール・ツァイスが展開していたブランドです。洗練されたデザインのボディは、コンタックスならではの唯一無二の存在感を放っています。コンタックスの魅力のひとつは、高度な光学技術を活かしたレンズによる、繊細で透明感あふれる描写力。また、コンパクトながらも、絞りやピントを自分で調整できる操作性のよさも評価されています。さらに、ダイヤルやボタンの触感にまでこだわった高級志向のデザインは、手に取る喜びを感じさせます。
現在でもコンタックスのカメラは高い人気を誇り、中古市場でも比較的高値で取引されています。
機種ごとに、実際の作例を見てみましょう。
1. CONTAX T2
1990年に京セラ・CONTAXから発売された「CONTAX T2」。頑丈で高級感のあるチタンボディと、描写力に優れたカール・ツァイスのゾナーT* 38mm F2.8レンズを搭載し、多くの写真家やセレブに愛用されてきました。操作はレンズ周囲のダイヤルで露出を調整するシンプルな設計で、F2.8時に露出オーバーになると自動で絞り込む機能も備えています。ただし、シャッター速度は最大1/500秒のため、高感度フィルム使用時は自動絞り込みに注意が必要。今なお人気が高く、高級コンパクトフィルムカメラの代表格として知られる名機です。
幅・高さ・奥行:119mm×66mm×33mm
重量:295g(電池別)
CONTAX T2の特徴
「CONTAX T2」の強みは、やはりカール・ツァイスレンズを搭載していること。ぼくは、レンズによる写りの差というものをあまり信じていなかったのですが、このカメラで撮った写真を見たときに、レンズの力というものに気付かされました。夜間や室内の複雑な光を捉える力には本当に目を見張るものがありますし、日常の些細な心の引っかかりを確かな「想い出」と呼べるものに引き上げる力があります。一方、「CONTAX T2」の弱点とも呼べる特徴に、オートフォーカスがときどき抜ける、つまりピントを外してしまうという点がありますが、これがむしろこのカメラで撮る写真をどうしようもなく愛しいものにしてくれます。
ピントの合わなかった写真というのは、二度とクリアに見られない光景であり、現実と思い出の隙間に記憶が転がり落ちてしまったような感覚をもたらしてくれます。これにより記憶を強く求める作用が働き、その光景が忘れられないものになるのではないかと思っています。中古相場が上がってしまい、なかなか手の届かないカメラではありますが、これ1台で全ての日常を作品にしてしまう力があります。記憶を邪魔しない、そんなカメラです。
CONTAX T2の作例


2. CONTAX T3

1990年代の高級コンパクトフィルムカメラブームの立役者「CONTAX T2」の後継機として2001年に発売された高級コンパクトフィルムカメラ「CONTAX T3」。コンパクトカメラの中でも、優れた操作性と高い性能のレンズを搭載し、プロの間でも愛好家が多いカメラです。 T2から継承されたカール・ツァイスレンズは35mm、最短撮影距離はT2のおよそ半分の0.35m。さらに、最高1/1200秒のシャッター・精度の高いマルチAFが搭載され、撮れる幅が格段に広がり、一眼レフに匹敵するほどの描写力を誇ります。ボディは、お馴染みの高級感のあるチタンで、T2よりも一回り小さく小型化。毎日ポケットに忍ばせ、街を歩くのを想像するだけで夢が膨らむ一台です。
幅・高さ・奥行:105.0mm×63.0mm×30.5mm
重量:230g
CONTAX T3の特徴
ふと、コンパクトカメラが家にあったことを思いだし、「CONTAX T3」を使い始めました。最初は「CONTAX T3」の魅力も分からず撮っていましたが、あるとき室内で撮ったシャープで高コントラストな描写が好きだと気づき、それからこのカメラの虜になりました。「CONTAX T3」が写す写真の立体感も大好きです。
CONTAX T3の作例


コダック(Kodak)
世界で最も歴史のあるアメリカの写真用品メーカー「コダック」のフィルムカメラは、誰でも簡単にフィルム写真が撮れる手軽さが魅力。シャッターを押すだけで撮影できるため、フィルムカメラの入門機として人気があります。
また、レトロなデザインにポップなカラーバリエーションと、持っているだけで気分が上がる見た目も、支持される理由のひとつ。プラスチック製の軽量ボディは扱いやすく、もし壊れてしまっても買い直しやすい価格帯なのも嬉しいポイントです。
実際の作例を見ると、そのシンプルさの中にも味わい深い写真が多く撮れることがわかります。
1. Kodak EKTAR H35N

2023年に発売された「Kodak EKTAR H35N」は、「EKTAR H35」の後継機として登場したハーフフレームフィルムカメラです。このモデルは、35mmフィルムを使用し、1枚のフィルムで通常の倍の写真を撮影できるハーフフレーム形式を採用。軽量でコンパクトなデザインと内蔵フラッシュを備えており、レトロさと現代的な機能を兼ね備えています。
幅・高さ・奥行:約 110mm×62mm×39mm
重量:約 110g
Kodak EKTAR H35Nの特徴
フィルムの価格が高騰する中で、もっと気軽にフィルムを使えるカメラとしてハーフサイズカメラの「Kodak EKTAR H35N」を選びました。軽くてコンパクトで、かわいい見た目なのにしっかり写るのが魅力です。ミラーレスのようにすべてがきれいに写るわけではありませんが、その場の空気感や記憶をフィルムに記録してくれるお手軽カメラとして、いつもバッグの中に忍ばせています。 ブレたりピントが合わなかったりすることもありますが、ぼやけた世界の向こうに見える被写体の笑顔が、当時の楽しかった気持ちを鮮明に思い出させてくれます。また、シャッターを押すだけの簡単操作なので、被写体との距離感が縮まるように感じます。
https://encounter.curbon.jp/gallery/mycamera-kodak-ektar-h35n/
Kodak EKTAR H35Nの作例


ローライ(ROLLEI)
ローライは、1920年に設立されたドイツを代表するカメラブランドです。中判カメラやコンパクトフィルムカメラの分野で高い評価を受けており、優れた光学性能と堅牢な金属製ボディにより、プロフェッショナルからハイアマチュアまで幅広く支持されています。
多くのモデルには、シャープで高コントラストな描写力に定評のあるシュナイダー・クロイツナッハ製レンズが搭載されているほか、カール・ツァイス社製の高性能レンズを搭載したモデルも存在します。
しっかりとした金属製のボディは耐久性に優れており、長く愛用できるカメラとして知られています。
では、実際の作例を見てみましょう。
1. ROLLEI 35T

「ROLLEI 35」シリーズは、1967年に初代が発売されて以降、多くの写真家を虜にしたカメラです。描写力に優れたカール・ツァイス社製の沈胴式レンズを採用しており、デザインもお洒落なので、旅行に持っていくのに最適な一台です。また、ピントを目測で合わせるアナログさも魅力の一つ。デジタルカメラが主流な現在だからこそ、そんなひと手間も楽しむことができるのではないでしょうか。
幅・高さ・奥行:103㎜×65㎜×32㎜
重量:370g
ROLLEI 35Tの特徴
「Rollei35」は、一生手放さないと決めた大好きなカメラです。特筆すべきは、そのコンパクトさ。手のひらにしっくり。ポケットにすっぽり。
これでフルサイズカメラなんだから驚きです。コンパクトさを実現するための沈胴式レンズや前面についたダイヤルは、デザイン上の魅力にもなっています。
操作性は、絞りもシャッタースピードもマニュアル。ピントは目測という究極のアナログ仕様。しかし、一つひとつの動きは滑らかで、ファインダーも輝くばかりに明るく見やすいので、気持ちよく撮影ができます。そして、写りがまた驚くほど良いのです。私は中判カメラをメイン、サブに35ミリカメラを持ち歩くのですが、ピントがはまったときのこのカメラは、中判に負けない写りをすることがあり、いつも現像が楽しみです。全てがマニュアルがゆえに少しばかり面倒ではありますが、使ううちに空間の光量や被写体との距離を感覚で分かるようになって行くので、自分の身体感覚が磨かれるカメラでもあります。
ROLLEI 35Tの作例


五光(GOKO)
五光は、1953年に創業された日本の光学機器メーカーです。かつては8ミリフィルム編集機やコンパクトフィルムカメラの分野で世界的なシェアを誇り、1980年代から1990年代にかけてはOEM供給を中心に年間400万台以上のカメラを生産していました。
五光のカメラは、高倍率ズームをはじめとした接近撮影に特化している点が特徴。また、コンパクトなデザインと操作のしやすさにより、初心者にも扱いやすいモデルが多く揃っています。さらに比較的手頃な価格帯のため、コストパフォーマンスの高さも大きな魅力となっています。
では、実際の作例を見てみましょう。
1. GOKO Macromax FR-350

「GOKO Macromax FR-350」は、五光が1998年に発売した35mmコンパクトフィルムカメラです。特筆すべきは、世界で初めて「10cm接写」を可能にしたコンパクトカメラであるという点。これまでのカメラの常識を覆す、「接写」に特化した画期的な一台です。
ピント調整は3つの撮影モードで切り替える方式。「ウルトラマイクロモード(U)」は0.1m〜0.3m、「スーパーマイクロモード(S)」は0.3m〜1.0m、「ノーマルモード(N)」は1.0m〜無限遠という構成で、被写体との距離に応じたきめ細かな撮影が可能です。
シャッタースピードも「1/300秒」「1/90秒」「1秒」の3段階に設定されており、露出やピントはすべて固定。シンプルな操作性により、フィルムカメラ初心者でも扱いやすい設計となっています。一方で、中級者にとっては接写の面白さや奥深さに気づかせてくれる、まさに新しい世界を切り拓く一台です。
幅・高さ・奥行:117mm × 63mm × 44 mm
重量:約190g(電池含む)
GOKO Macromax FR-350の特徴
僕にとって理想とするカメラは、目の前の大切な瞬間を逃さないカメラでした。
そんなカメラを探して行き着いたのが、ピント合わせのタイムロスがない固定焦点、ポケットにも入るサイズ感と軽さが両立できているカメラでした。有名なところでいうと『写ルンです』がこの条件に該当します。「GOKO Macromax FR-350」は『写ルンです』と同じ固定焦点、圧倒的な軽さ、力強い青の発色を備えていながら、『写ルンです』にはないシャッタースピードの変化、スローシャッター機能、10cm〜∞の撮影距離に対応しているなど、誰もがお手軽に、かつアイディア次第でさまざまな撮影に対応できる応用力があります。
ポケットに入れて持ち運んだり、常に手に持っていても邪魔にならず、「撮りたいと感じた瞬間」をそのままに撮ることができる。僕にとってこれ以上のカメラはありません。
https://encounter.curbon.jp/camera/mycamera-goko-macromax-fr-350/
GOKO Macromax FR-350の作例


ヤシカ(YASHICA)
1949年に創業されたヤシカは、かつて日本を代表する光学機器メーカーとして世界的に名を馳せたブランドです。特に1950年代から1980年代にかけては、高品質なレンジファインダーカメラや一眼レフカメラを数多く世に送り出し、多くの写真愛好家やプロフェッショナルから高い支持を集めました。
なかでも注目されるのは、ドイツの名門・カール・ツァイスとの協業により実現したレンズの搭載。繊細で透明感のある描写力は、ヤシカの大きな魅力のひとつです。また、高性能でありながら比較的手の届きやすい価格帯で展開されていたことも、多くのユーザーに親しまれた理由といえるでしょう。シンプルかつレトロなデザインもまた、ヤシカの個性。時代を超えて愛され続ける、フィルムカメラの原点のような存在です。
では、実際の作例を見てみましょう。
1. YASHICA ELECTRO 35

「YASHICA ELECTRO 35」シリーズは、1966年の登場以来、長年にわたって生産され続けた名機です。コンパクトなボディに加え、明るいF1.7の大口径レンズを搭載しており、幅広いシーンで活躍できる撮影の自由度の高さが最大の魅力。
その使いやすさと描写力から、現在でも多くのフォトグラファーに愛され続けています。手初めてのフィルムカメラとしてもおすすめの一台です。
幅・高さ・奥行:143㎜×88㎜×48㎜
重量:610g(ボディのみ)
YASHICA ELECTRO 35の特徴
「YASHICA ELECTRO 35」シリーズは比較的安価に手に入るレンジファインダーカメラですこのカメラの特徴はなんといっても40mm/F1.7という明るくて素晴らしいレンズがついていること。「ろうそく1本の光でも写る」が開発コンセプトだったらしいのですが、F1.7の明るさとスローシャッターによって、室内や夜間でも撮ることができて、写りがとても良いと感じます。高感度フィルムの多くが終売し高価になってしまった今は、なおさらありがたいですね。同時代の多くのレンジファインダーカメラとは違って絞りを自分で設定できるので、ポートレートなどでもレンズの明るさを生かして綺麗なボケをつくることができます。本格的な一眼レフカメラと気軽なコンパクトカメラのちょうど中間くらいの存在で、人によっては「最高にちょうど良いカメラ」になり得る、おすすめの一台です。
https://encounter.curbon.jp/gallery/mycamera-yashica-electro-35/
YASHICA ELECTRO 35の作例


さいごに
今回は、全10社のメーカーからコンパクトフィルムカメラをご紹介しました。
気になる一台には出会えたでしょうか?
ぜひ、自分だけのお気に入りを見つけて、日常の風景をフィルムで残してみてください。
きっと、撮る時間そのものが、かけがえのないものになります。