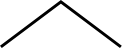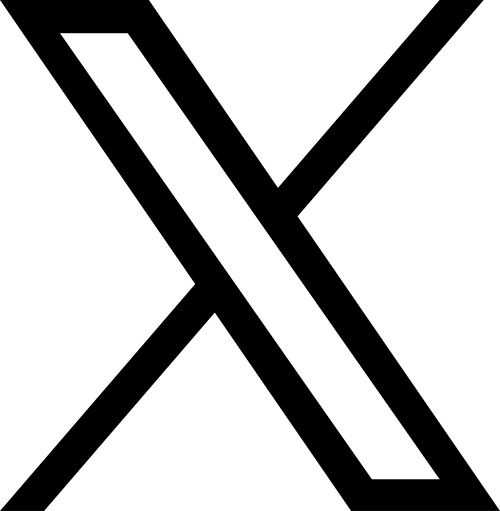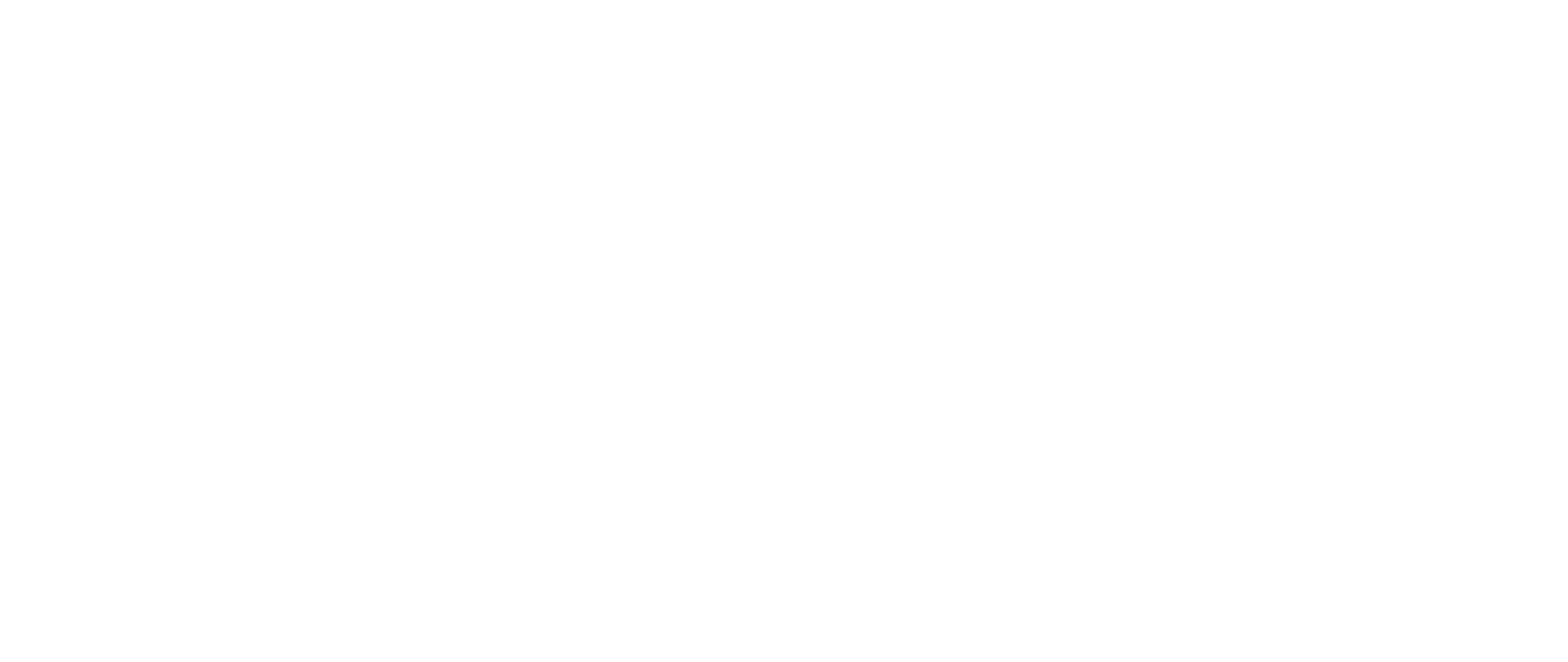「枠外」の物語を撮るということ#写真家放談 |児玉浩宜
PROFILE

PROFILE
児玉浩宜
1983 年、兵庫県生まれ
NHK で報道カメラマンとして勤務後、フリーランスのフォトグラファーとして独立 2019年には香港民主化デモを取材し、写真集『NEW CITY』および『BLOCK CITY』を発表。
2022年3月以降、ロシアによるウクライナ全面侵攻を取材し、テレビ、雑誌、ウェブメディアへの映像・写真の提供や執筆活動を行う。写真集『Notes in Ukraine』を制作。編集者とメキシコを旅をした記録『わたしはどこへゆく?メヒコ長距離バス旅』(共著)。
そもそもフォトグラファーに強い憧れがあったわけではない。高校時代にロバート・キャパや一ノ瀬泰造の著書を手にしたことはあった。それよりも映画が好きだった。映像に関わる仕事として選んだのはテレビ局での報道カメラマンだった。

事件や災害報道で忙しい日々だったが、カメラマンは常に現場に身を置けるという特権は気に入っていた。だが、仕事はそれだけではない。番組や企画者の仕事がある。
事前に用意した企画書から計画を立て、それに沿ったものを成立させなければならない。わかりやすさも求められる。組織の一員として動くより、一人で知らない場所を訪ね歩く方が性に合っていた。休暇の度にカメラを持ってひとり海外へ。テレビで使う大型のカメラより、小さな35mmフィルムカメラのほうが見知らぬ人との距離を縮められる気がしたし、何より自由だった。結局、仕事を辞めたときも手にしていたのはフィルムカメラだった。

どちらかというと写真に対して「我」が強くないほうだと思う。そのせいか流されるまま、なりゆきで被写体に出会うことが多い。
2019年の香港民主化デモが始まった時、現地に住む友人から「早く来い!来なければお前は後悔する!」と強く誘われた。慌てて翌日、香港を訪れると「うわっ、本当に来たのか!」と驚きながら笑われた。だがその後、毎月通って撮影することになる。
デモ隊と治安当局との衝突は毎晩のことだった。抗議の現場にいる友人たちを撮影していたが、彼らが早々に「もう帰ろう」と言うこともあった。彼らの部屋に戻るといつものように麻雀を始めた。深夜、時には明け方までそれは続く。私はルールを知らないので、おしゃべりしながら眺めることになる。将来のことや、仕事のこと。どこのワンタン麺がおいしいとか、そんな話が続く。唐突に「日本人として香港のデモをどう感じてるの?」と聞かれた。うーん、と唸るばかりで、言葉が出てこない。考えながら一人で外を歩いた。

すでに真夜中。さっきまで抗議を続けていた人々の姿はなく静まり返っていた。路上にはデモ隊が作りあげた即席のバリケードが残されていた。ゴミ箱やレンガ、段ボールに取り外したガードレール。それらを眺めていると、茶道の「見立て」という言葉が思い浮かんだ。物を本来の用途から切り離し、別の意味や価値を見出す日本特有の感性だ。見当違いかもしれないが、目の前にあるバリケードに私はそれを感じた。大抵、翌日には撤去されてしまうという儚さもある。声高に叫ぶ民主活動家の眩しい正論より、物言わぬ物体には静謐の中に鋭く訴えかけるものが漂っているような気がした。
それから私は毎月現地へと通い、現れては消えるバリケードを記録することになった。問われた答えがそこにあると思った。


ロシアによるウクライナへの全面侵攻。すぐにウクライナへ向かった。コロナウィルスによって自由に動けなかった反動で、体も極端な環境を求めていたのだと思う。何より「現代の戦争とはどういうものか」という好奇心があり、できればそれを写真に捉えたいと思った。人類が何度も繰り返してきた戦争という絶対悪。対して私の正義感などというものは情けないほど脆い。いくつもの悲惨な現場を訪ねたが、理解を超える惨状にうまく対応できず、善や悪といったことばかり考えるのが、次第に疎ましくなっていた。

ウクライナへ通ううちに、現地に住む親子と親しくなった。どういうわけか何度も魚釣りに誘われる。戦時下の魚釣り。意味がわからない。
不自由な生活が続いているはずなのだが、やることがあまりにも牧歌的だ。しかし、竿先を見る彼らの顔は真剣である。一心に集中することで、どうしようもない現実を振り払おうとしているのだろうか。一度、巨大な魚がかかったが、糸が切れて逃げてしまった。それでも彼らは興奮していた。その理由もわからなくはないが、やっぱりどこか奇妙だった。

私にとって撮影は旅に似ている。事前にスケジュールを決め、「これをしよう」と願望を抱くが、途中で思いがけないことに遭遇して、当初の目論見が崩れることもある。すべて相手のペースに委ねられ、「もうどうにでもなれ」という境地に至ることもしょっちゅうだ。そして自分ひとりが無力だと思ったり、妙な発見に気づいて嬉しくなることもある。それから本当の旅が始まるように、撮影もまたそこから始まるような気がする。
戦闘が続く前線を取材するため、ロシアとの国境の街、ハルキウに滞在していた。そこで偶然の出会いが重なり、今はスケートボードに乗る若者たちのコミュニティの撮影を続けている。理由は単純で、かっこいいからだ。街にミサイルが落ちる音が響いても、彼らはスケボーの板から降りることはない。彼らと時間を過ごしたいと思った。


カメラがあって本当によかったと思う。撮影係でもなんでもいい。結局のところ「ここにいてもいい?」という許しを得るために、私はカメラを持っているのかもしれない。実際のところ、彼らにとって私はスケボーもまともに乗りこなせず、ウクライナ語もロシア語も話せない、どうしようもない存在だろう。でもカメラがあるのでなんとかコミュニケーションが取れている。たいてい彼らの代わりに酒やタバコを買う役回りを任されるのだが。

写真はフレームの中に収めるものだけれど、現実は往々にして枠に収まりきらない。戦時下の街でスケートボードに乗り続ける若者たち。彼らの日常もまた、ニュースで語られることのない「枠外」の物語だ。そして、その「枠外」にこそ私は魅力を感じる。
相変わらず計画は思い通りにはいかないが、今の私がなりゆきによって形作られたものであったとしてもそれで構わない。心を動かされるものには正直に向き合っていきたいと強く思う。