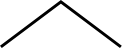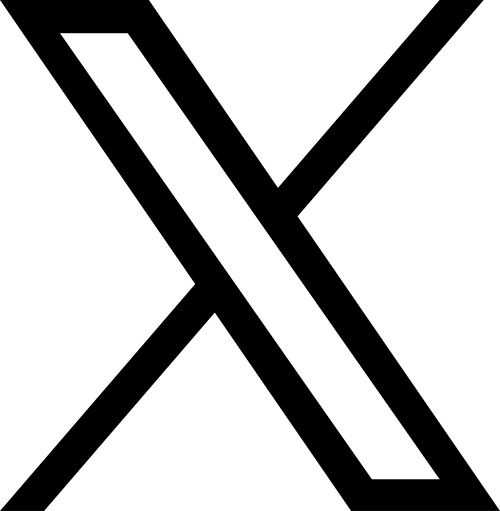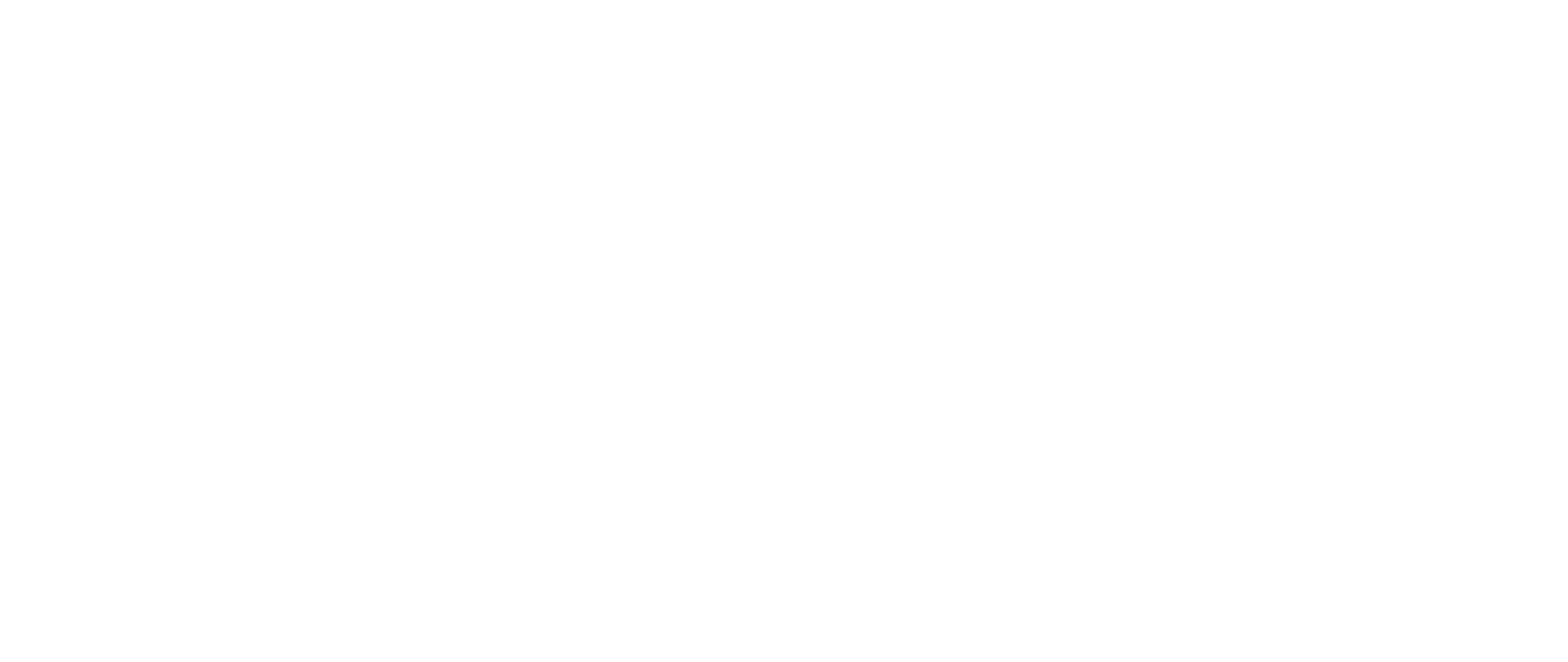《インタビュー》写真家・小澤太一が道東で見た「回」。1万年の歴史の中に在る人や自然のすがた
写真家・小澤太一による写真展「回」が、キヤノンギャラリー S(東京・品川)にて、2025年11月10日(月)まで開催中だ。
小澤太一の写真展は、2025年6月にNine Gallery(東京・北青山)にて開催された「HEROES」以来。

入口をくぐると、目の前には静謐な黒の世界が広がる。順路の定められていない空間をライティングが照らしモノクロ写真が並ぶ光景は、まるで道東の深い自然の中に迷い込んだよう。耳をすませば、「回」の撮影地である道東で録音したという自然の音が流れていた。
モノトーンの世界を散策しながら、全84点の作品を鑑賞できる同写真展。展示にかける想いや小澤が見た「道東」について、詳しく話を聞いた。
PHOTOGRAPHER PROFILE

PHOTOGRAPHER PROFILE
小澤 太一
1975年、名古屋生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業後、アシスタントを経て独立。人物撮影をメインに、写真雑誌での執筆や撮影会の講師・講演など、活動の範囲は多岐に渡る。ライフワークは「世界中の子どもたちの撮影」で写真展も多数開催。主な写真集に『ナウル日和』『SAHARA』『赤道白書』『HEROES』など。身長156cm 体重39kgの小さな写真家である。キヤノンEOS学園東京校講師。日本写真家協会会員。
@kozawataichi https://www.kozawataichi.com/モノクロや抽象的な描写でさまざまな解釈を可能に

ーー小澤さんの作品は、前回の写真展「HEROES」でも観られたようなカラフルな人物写真のイメージが強いですが、今回はテイストが変わりましたね。
今回は全体的に「これはいったい何を撮っているんだろう?」と思わせるような見せ方にこだわりました。何を撮影した写真なのか、どんな状況を写した写真なのかが、ひと目ではわからない。だけど見ると何かを感じる、そんな表現を今回は大切にしています。

そのため画角や角度、レンズの効果などを最大限に活用しましたね。撮影距離も遠影や超接写など、いろいろ試しました。ちなみに、すべての写真をモノクロにしたのも、情報量に制限を加えるためです。被写体の本当の色がわからないからこそ、さまざまな見方ができると思います。
ーー人物写真の切り取り方も、過去作品とだいぶ違うように思われます。
そうですね。今までは、世界各国で出会った方々を写真の“主役”として撮影してきたんですよ。その国での出会いやその人と過ごす瞬間を、かっこよく魅力的に残そうとしたというか。

一方、今回展示する写真は真逆のアプローチをしました。個人を目立たせようとする意識を可能な限り消し、道東という環境や長い時間の一部として、人がひっそりと“在る”様子、いわゆる人の個性が前に出ているわけではないけれど、その地で生きている存在としての強さが見えるように工夫して撮影しましたね。

めぐりゆく道東の時間、ただそこに在る自然と暮らし
ーー北海道東部、つまり「道東」を今回の撮影地に選ばれた背景を教えてください。
コロナ禍で海外渡航ができなくなり、日本国内を旅しながら被写体を探していたときに、道東という場所を知ったんです。北海道にはさまざまな土地がありますが、なかでも道東には「荒々しく何もない地」という印象を持ったんですね。
いわゆる都会的なものはほとんどなく、交通インフラの面でも決して便利ではない。道東に住む人は「稲作も酪農もできず畑にもならない、使い道のない土地だ」と言っていたほどです。
ただ、そこには人の文化が侵食していない圧倒的な自然が広がっていて。歩いているだけで光がとても綺麗だったり、動物や鳥の声がしてきたりするんです。

僕にとって、そうした手つかずの自然の姿は未知の世界であり、そんな道東に強く惹かれました。気づけば撮影のために二拠点生活を送るほど、深く関わるようになっていましたね。最終的に、道東に通ったり暮らしたりしながら、4年半かけて撮影を続けました。
ーー展示のタイトルである「回」には、どのような想いが込められているのでしょうか。
僕自身がまず思い描いたのは、命の循環のイメージです。都会で暮らしていると、生き物の死に触れる機会は多くありませんが、道東では森を歩いていると鹿の亡骸を目にすることもある。そうした光景を通じて生と死がとても身近に感じられたんです。

また、縄文時代から続いてきた道東の長い歴史も「回」に込めた大切なテーマの一つです。道東では1万年以上前から鮭を獲る漁を行っており、熊や鹿などの自然の恵みを受けながら人々が暮らしてきた歴史があります。悠久の時間のなか、変わらない自然とともに文化や伝統が引き継がれてきた連なりのイメージもこの言葉に重ねていますね。
さらに「カイ」という音は、北海道の語源とも関わりの深いアイヌ語で、「この地に暮らすもの」という意味を持っています。「回」という漢字のかたちも、どこかアイヌ模様のように見えて。そうした偶然の重なりにも、いい巡り合わせを感じました。
ただ、「回」というタイトルはシンプルな言葉だからこそ、見る人が自由に解釈できると思っています。展示を見ていただいたうえで、それぞれの「回」を感じてもらえたらうれしいですね。
未知への興味に突き動かされた150万枚
ーー道東でシャッターを切ろうと思ったのは、どのような瞬間でしたか。
特に「この瞬間にシャッターを切ろう」とは決めていませんでしたね。むしろ現地では、動物の一瞬の表情や動きといった、一期一会の出会いを逃さないよう、常にカメラを構えていました。
今回の展示で選んだ写真は84枚ですが、道東での4年半の間に150万枚もの写真を撮ったんですよ。道東には魅力的な被写体が多く、1日で1万枚以上撮る日もありました。

ーー写真展のステートメントにも「被写体」という言葉が登場していましたが、小澤さんにとって「被写体」とは何でしょうか?
“未知なるものへの興味”でしょうか。いつも撮影地を選ぶときには「知らないから行ってみたい」という衝動から始まります。だから、下調べをしっかりして被写体を選ぶといったことはあまりしないですね。
今回、道東を旅しようと決めたときも、その土地の歴史などは何も知らなかったんです。ただ、写真を撮る過程で多くの人に出会い、その土地の歴史や風土について教えてもらうことで、だんだんと理解が深まっていきました。
たとえば、今回展示する作品のなかには、斜里町で撮影したねぷた祭りの写真があります。この写真を見た人の中には「北海道なのにねぷた祭り?」と思う方もいるかもしれません。

僕もこの写真を撮ったときは、特に深い背景までは知りませんでした。ただ、ねぷた祭りを現地で見たあと、地元の方と居酒屋で話すうちに、その由来について教えてもらったんです。
それは1807年、北方警備のために津軽藩から100余名の和人が派遣されたものの、北海道の厳しい寒さからひと冬で72名が亡くなってしまい、それをきっかけに斜里と津軽、弘前の間で交流が生まれ、ねぷた祭りが斜里町に伝わった……というものでした。
あらかじめ被写体のことを知って撮りに行くよりも、撮る過程で被写体のことを知っていく。そこにおもしろさを感じるから、僕は旅をしながらファインダーを覗き続けているのだと思います。
「回」をさまよい、追体験してほしい
ーー来場する方に、写真展「回」をどのように楽しんでもらいたいですか。
作品の見方は自由なので、好きなように見ていただきたいです。いろいろな解釈ができる展示になっていると思うので、ぜひさまざまな視点で鑑賞してみてください。
今回はキヤノンギャラリーSの広々とした空間を活かして、会場全体を「回」の字のような二重構造にしています。そのため外側と内側の展示で、雰囲気の変化を感じていただけるはずです。森や町を歩いている時に感じる「ここは少し空気が違うな」「雰囲気が変わったな」といった感情の揺らぎや深まりをこの空間で再現できたらと思っています。

また「回」には、あえて明確な動線を設けていません。道東で僕自身がそうだったように、森や海、人びとの生活の中をさまよっている感覚を、来場者の皆さまにも追体験していただけるとうれしいです。
ーー最後に、小澤さんが目指す写真家像があれば教えてください。
何にも流されない、強い写真家でありたいですね。自分の興味を見つけたら長い年月をかけてでも決めた道を進み続けられる、仙人のような写真家になりたいです。写真を通して、おもしろいことをずっとやっていきたいですから。
▼Information
小澤太一写真展「回」
【開催期間】2025年10月2日(木)〜11月10日(月)
【時間】10:00-17:30
【定休日】日曜・祝日
【場所】キヤノンSタワー1階 キヤノンギャラリーS
【住所】東京都港区港南2-16-6
【入場料】無料
取材・執筆:加藤由梨