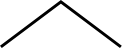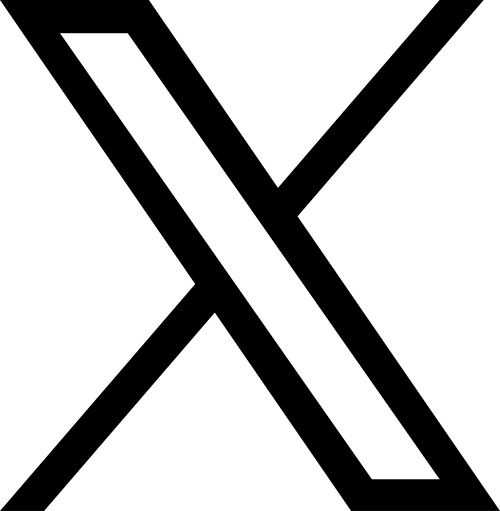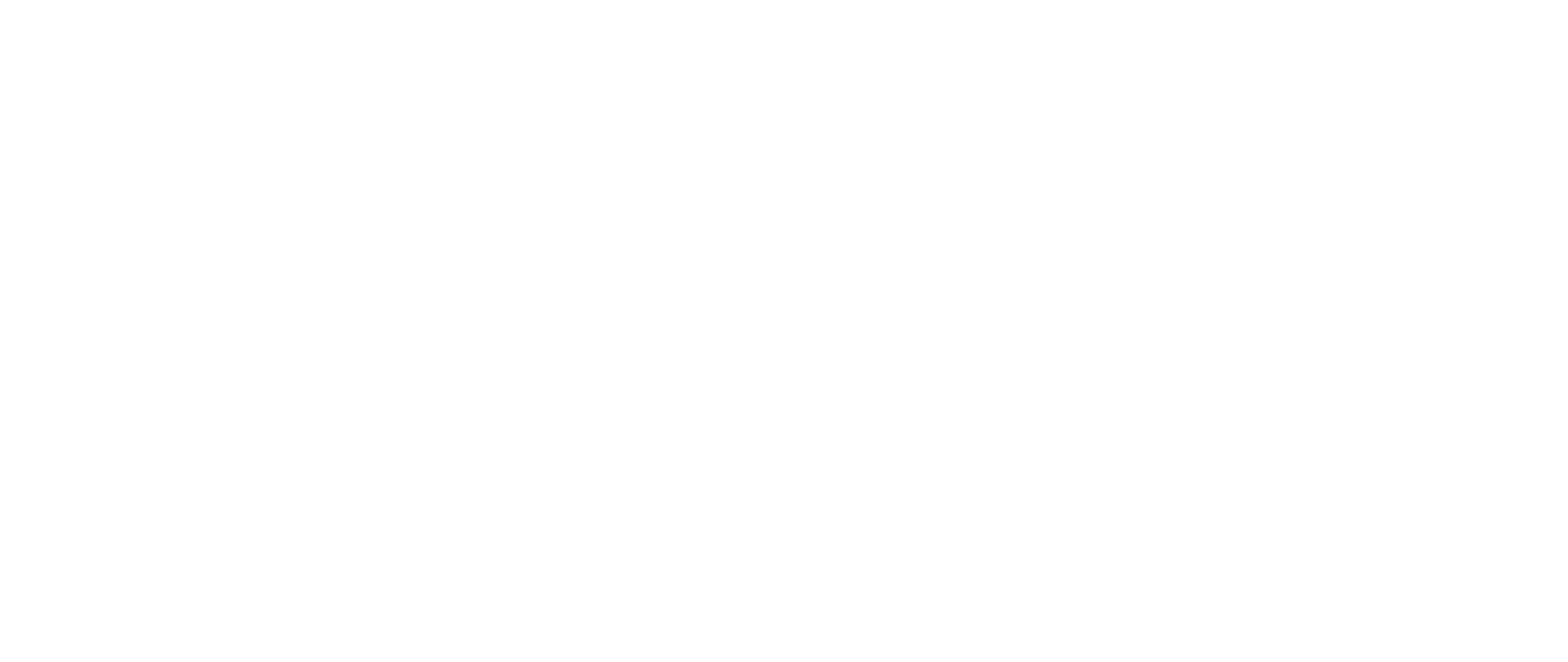【景色になる家具たち】「ただあるように、その手が動くように彫っていくと、自然に近いものができる」atelier.f 渡邊文矢
日本各地で家具をつくる作り手のまなざしを通して、ものづくりの現在地を見つめる連載「景色になる家具たち」。日々の暮らしに寄り添い、使うほどに深みを増す家具には、素材と向き合い、手を動かし続ける人々の静かな熱が宿っています。

今回ご紹介するのは、岐阜を拠点に活動する彫刻家、atelier.fの渡邊文矢さん。インスタグラムのフォロワーは10万人。伝統工芸の技術を基盤としながらも、繊細で木に宿る魂を解き放つような作品には、観る人を釘付けにする魅力があります。

PROFILE
PROFILE
渡邊文矢
岐阜県を拠点に活動する彫刻家。京都伝統工芸大学校で仏壇彫刻を学んだ後、富山県の伝統工芸である井波彫刻の工房に弟子入りし、約10年間修行を積んだ。欄間や置物など伝統的な彫刻技術を習得する一方で、独自の表現を模索し続け、2011年に独立。伝統工芸の技術を基盤としながらも、「考えないで作る」という独自の創作哲学を追求し、木の持つ本来の姿を尊重した作品を制作している。インスタグラムでは多くのフォロワーを持ち、繊細で生命力あふれる木彫作品が高い評価を受けている。現在も伝統的な彫刻の仕事と並行しながら、自身の表現を追求し続けている。
@atelier_f._/
作品を通して人と繋がっていくことができる

──現在の繊細な作風に至るまでの経緯について教えていただけますか?
作品自体は20年近く前から作っているんです。元々は伝統工芸をやりたいと思って、京都伝統工芸大学校で仏壇の彫刻を学びました。その後、富山県の井波彫刻というところに弟子入りして、欄間や置物など伝統的な彫刻を作っていたんですね。そこで10年ほど修行していたのですが、その間にも今のような作品を個人的に作っていました。
──そもそもどうして伝統工芸の道を選ばれたのですか?
あまりいないと思いますが、中学校や高校のときから木を彫るのが好きだったんです。部活は運動部に入っていたものの、家に帰ってきてからインターネットなどの見よう見まねで、リアルな鳥や魚などを作っていました。

──木を彫るのが好きだったというのは、何かきっかけがあったのでしょうか?
元々物を作るのが好きだったんです。父親も趣味で陶芸をやったり家のフェンスを作ったりするDIY好きで、そういう環境はあったので、中学生の頃は、そこら辺に落ちていた枝をカッターナイフで削って作ってみたりして。

ただ、それは本当に遊ぶ感じでやっていたんです。その延長線上で、たまたま木を使って何か作ってみたら面白いかなと思ってやったらとてもハマってしまって。自分が楽しいと思ってやり始めたことが今もずっと続いているという感じです。

伝統工芸師に弟子入りして、親方のもとで木を彫る技術、刃物の使い方を学びながら欄間や寺社仏閣の彫刻をしてきました。5年間で一人前になり、このまま伝統工芸の道を進んでいくのか、自分が表現したいものを彫刻で表現していく道を進むのか、この二択が僕の中でありまして。
──今作っている作品と方向性はだいぶ違いますね。
結果としては、お寺の彫刻や和菓子の型をつくる仕事をしながら作品づくりをしています。

──伝統工芸の修行で学んだことは、現在の作品にどのように生かされていますか?
技術的な部分では生かされていますし、お客さんとのやり取りも学びました。ただ、表現においては、伝統工芸の仕事をするときとは考え方を逆にしています。伝統工芸の仕事では、お客さんがどういうものを欲しいのかを考え、要望に応えることを大切にします。一方で自分の作品を作るときは全く考えないようにしています。意図をしないで作るというか、誰かに「こうした方がいい」と言われるだけでも流れが変わってしまうので、それは避けています。木を削るという行為は同じですが、全く別物ですね。

──独立後、どのような流れで現在の作風に繋がっていったのでしょうか?
独立した後、手作り市のようなイベントに出展してみたんです。そのときは「このままやっていっても生活できないかな」と思っていたのですが、お客さんの反応がとても良くて、こういう作品を作り続けてもいいのかなと思えるようになりました。なかには「これが欲しいから」とわざわざ銀行までお金を下ろしに行って戻ってきて、「宝物にします」と言って買ってくれた人もいて。今まで単に自分の中の悶々としたものを作品にていただけでしたが、作品を通して人と繋がっていくことができるんだなと感じました。

考えないで作る、木彫刻
──作品づくりにおいて大切にしていることは何でしょうか。
考えないで作るということを一番に大事にしてきましたね。親方のところでは考えながら作っていくものでしたが、そうではなく、自分を無にした状態で作ったときに生まれるものが作っていて楽しいし、できあがったものが生き生きしているように感じました。ただ、考えないで作ろうということを考え始めてしまう時期もあって、禅問答のようになってしまうんです。去年か一昨年くらいまではそれでだいぶ悩んでいました。何百個も作っていく中で、だんだん昔のようには作れなくなってしまって。悩めば悩むほど作品自体も悩んだ表情になっていってしまいました。

──その悩みはどのようにして乗り越えたのでしょうか?
この細い作品を作ったときに何か一つ突破できたような感じがあって。具体的には、使う刃物を変えたんです。今まで使っていた「箱のみ」という平たい刃物から、普段はあまり小さな作品には使わない「大きな丸のみ」という道具に変えました。箱のみだと思った通りに彫れるのですが、丸のみで彫っていくと予想外の通り道ができて、造形的に面白くなるんです。そうすると図案にとらわれなくなって、作品自体がなりたいようになっていく感じがして、今の彫り方の原点になっています。

──道具を変えたことで作品に心境の変化はありましたか?
それまでのやり方にこだわらなくなりました。以前はこのやり方がいいと思ったら、どうにかそこに戻ろうとして、考えないで作るということを考えてやっていたんです。それが新しい道具を使うことで、かえって昔に戻れたような感じがして。道具を変えることで昔にとらわれないからこそ、過去と同じ気持ちでできているという感じがします。

──作品を彫る際の気持ちはどのようなものですか?
気持ちいいですね。この作品を作っている最中は、気持ちの良い縁側でぼーっとしているような、漂っているような感じでした。作品は自分自身との対話のようなもので、スケッチブックにすごいスピードで落書きのようにラフを描いて、それを通して自分の気持ちを理解して、作品を作っていくんです。ただ、2次元を3次元にするときに、どういう彫り方をしたらかっこよくなるかは少し考えながらやります。

──作品を受け取る人にはどのように感じてほしいですか?
そもそも、木を彫ることをとおして自分自身が癒されているんだと思うんです。多分そういう気持ちで作るから、見てくれた人にも何か伝わるのかなと思います。あまり一生懸命やりすぎると、見る側もつらい気持ちになってしまうかもしれません。

だから人それぞれ感じ取ってくれたらいいなと思います。僕が「こういうふうに思ってほしい」というよりは、見た人が自由に解釈して楽しんでほしいですね。ただ単にそこにあるものを作りたいと思っているので、部屋の中でも特別な扱いはせず、ただ飾ってくれたらそれで嬉しいです。昔は彫刻とは部屋の空間を全部支配するものというような意気込みで作っていましたが、最近は部屋に馴染んでくれるようなものであったらいいなと思っています。
なぜ生きているのか、と悩んでいた時期

──ただあるようにある、という言葉について、もう少し詳しく教えていただきたいです。
人もそうですが、いろいろと考えて、あんなふうになりたい、こうふうになりたいと思うけれど、根本的な部分で言えばただそこにあるだけでいいと思うんです。だから、作品も何かを主張するのではなく、ただそこにあればいい存在を目指して作りたくて。

高校生の頃になぜ生きているのかと悩んでいた時期が、この思想の原点となっていますね。実家が山の方に引っ越して、誰も足跡のついていない雪原で一人寝そべったとき、「僕が何をしようと何を思おうと、空から見たら何も変わらないんだろうな」と思って、ただやりたいことをやればいいんだ、ありたいようにあればいいと思えました。
──そうしたありのままという感覚は、木と向き合うときにどうつながっているのでしょうか。
木は彫らないでそのまま立っている姿が一番美しいと思うんです。だから、そこにちょっとでも近づけたらいいなと思います。木の塊があって、それを自分の意思で彫ろうと思うと人間が作ったものになってしまいますが、ただ手が動くように作っていくと、すごく自然に近いものができるんじゃないかと思っています。これをやるにはすごく技術が必要で、その技術を身につけたのが伝統工芸だと思っています。技術は見せるものではなく使うものだと思ってやっています。

人は心を形にできる。あるがままの自分を映す創作とこれから
──今後の創作活動についてはどのようにお考えですか?
今まで通りこのまま続けていきたいです。年を取っていけば、年を取った作品が作れるようになると思います。考えが深まっていくのか、もっと適当になっていくのかわかりませんが、そのときの自分らしい作品が作れていれば、それが正解なんじゃないかと思います。年を取って10年後、20年後も今と全く同じものを作っていたら、それはおもしろくないと思うので、変化していきたいですね。