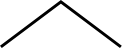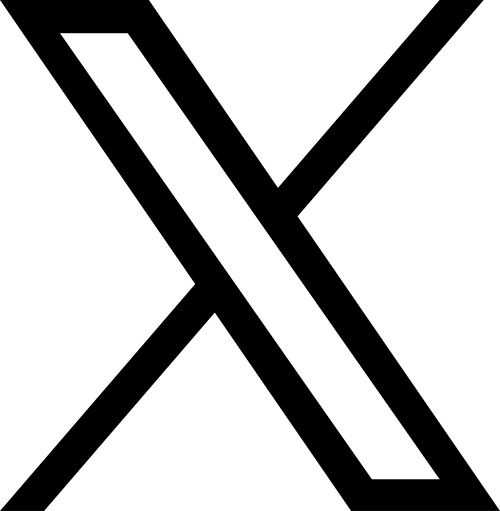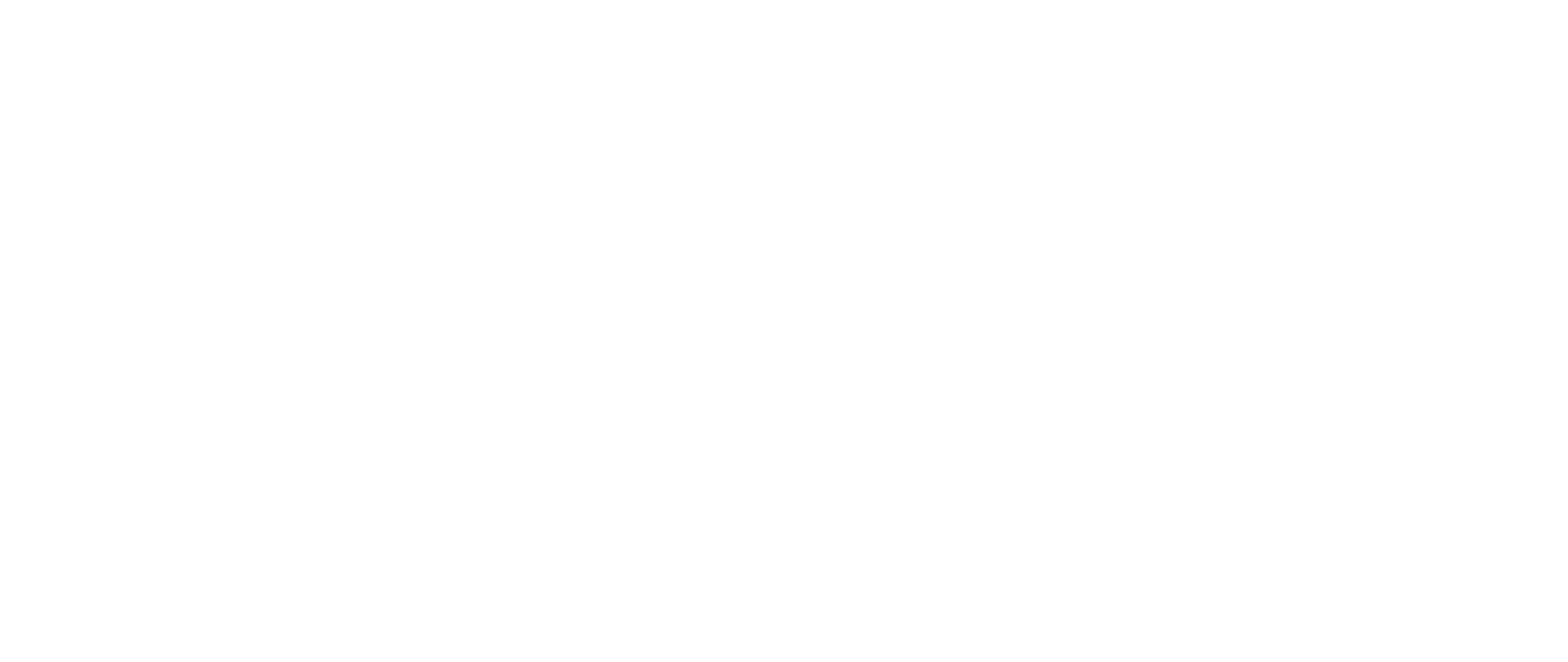【景色になる家具たち】石巻工房が紡ぐのは、ただの家具じゃない。人間同士のつながりと、コミュニティを支えるもの <インタビュー完全版>
日本各地で家具をつくる作り手のまなざしを通して、「ものづくりの現在地」を見つめる連載「景色になる家具たち」。日々の暮らしに寄り添い、使うほどに深みを増す家具には、木と向き合い、手を動かし続ける人々の静かな熱が宿っています。
今回スポットを当てるのは、「DIYメーカー」としてDIYの可能性をデザインの力で押し広げる石巻工房。
彼らの家具は、シンプルで機能的なデザインが特徴です。しかし、その魅力は美しい家具を生み出すことにとどまりません。カフェやゲストハウスの運営を通じて幅広い「場づくり」を展開し、被災した石巻の未来を紡ぐ活動を行っているのです。ENCOUNTER編集部は、その活動の根源に迫りました。

未曾有の災害からはじまった、コミュニティとものづくりの再生
石巻工房の始まりは、東日本大震災という未曽有の災害だった。
震災後、復興支援として大量の規格材(2×4、2×6材など)が石巻に届けられたものの、それを使う大工や職人は足りていなかった。そのような状況下で、東京から持ち込んだハンドソーや丸鋸といったDIYレベルの道具で「自分たちで何かやってやろう」という思いが石巻工房の原点となった。屋外で映画を上映する祭りの際に座るものがなく、寸法も正確に測れない中で「誰でもできる」家具を作ったのが始まりである。


石巻工房 「被災から1年2年たっても、なかなか現地では職人さんに頼みづらい状況が続いていたので、プロの職人さんたちではない人でも作れるもの、という制約が出てきたんです」。
この「平易な技術」「誰でもできる」という制約が、かえってデザインに創造性をもたらし、海外のデザイナーからも「参加したい」というオファーが来るほどになったという。

震災当初から海外からの支援が多く入り、ハーマンミラーとのワークショップではアメリカ本部などからもデザイナーが来日。地元の高校生たちと新しい家具をデザイン・制作する活動を行った。また、ハーバード大学の学生が震災後から活動のリサーチに訪れるなど、自然と海外との繋がりを意識する出来事が多くあったという。この経験が、石巻工房が当初から海外に向けて活動を発信する流れを生み出したのだ。

近年では、チリの山火事などへも図面を提供し、現地の人々が家具を制作してコミュニティ作りに活用する活動も行われている。
広がり続ける、家具づくりを通じた輪
近年ではカリモク家具との業務提携を機に、新シリーズ「Maker Pack」ラインが発表された。

「Maker Pack」の最大の特徴は、日本の里山から得られる広葉樹を活用し、環境負荷が低く持続可能な森を支える新たな木材料として注目されるGLT(ギャザード・ ラミネーティッド・ティンバー)という新しい素材の使用している点と、フラットパック形式での提供を行っている点だ。GLTは、カリモクが管理する森の未利用広葉樹(ナラ、クリなど)を小さく切って接着したもので、通常チップになったり燃やされたりする材を有効活用する取り組みである。

フラットパック形式は、コストカットのためではなく、顧客自身が組み立てることで「元々ある(DIYの)精神」を感じてもらうため、そして海外発送時のCO2排出量削減という環境への配慮から採用された。カリモクの高い技術力により、組み立て家具でありながらも驚くほどの精度を誇る。
石巻工房 「里山の資源をどうやって活用していくのか、それからどうやって環境に寄与していくのか、ROOTED IN NATURE.(自然とともに自然に根ざしてどうやってやっていけるか)を大切にしています」。
一方、当初から石巻で作られている「The Originals」ラインでは、能登半島の震災をきっかけに始まった新たな支援の取り組みとして、能登ヒバが活用されている。この木材は防虫成分を含み、石巻工房の製品に使うことで継続的に仕入れ、地域を支える活動に繋げている。


このように石巻工房の活動は、物理的な場所にとどまらない「チーム」の広がりを見せているのだ。デザイナーや協業企業はもちろん、ロンドン、マニラ、ベルリン、デトロイト、韓国(釜山)、シンガポール、ミュンヘン、メキシコ、スカンジナビア、バリといった海外のコミュニティも、石巻工房の図面をもとに家具を制作し、コミュニティに貢献している。これは「石巻工房が主導せずに、現地でコミュニティを支えるための家具とものづくりの活動が生まれている。
石巻工房 「そもそもは自分たちでコミュニティの問題を解決していくことが(活動の)基本です。結果、家具を作ることになり、それを提供することに繋がっています。地域に根ざした活動を後から付け加えたのではなく、元々が地域にあり、そこから世界へと広がっていったんです。(石巻工房の中の人間たちは)小さなチームかもしれませんが、コミュニティだと思ってるんですね。それが広がっていくと、もうワンチームで世界でやっていけるんじゃないかと思います」。

今後、石巻工房は海外への展開をさらに強化し、石巻工房のデザインと思想、「Maker Made」という理念と家具を広めていくことを目指している。そして、国内においても「何かあったときに、その一つのケースとして(石巻工房が)活用されるような存在であり続けたい」と語る。
Made in Localについて;https://ishinomaki-lab.org/news/news/made-in-local/
Maker Packについて:https://kobo-shop.net/collections/maker-pack/
石巻工房の活動の根底には、「人間同士の繋がりとコミュニティを支えるもの」というプリミティブな欲求が流れている。
人と人、地域と地域を繋ぎ、その繋がりから生まれる新たな価値を創造し続けているのだ。彼らの活動は、まさに「景色になる家具」という言葉が示すように、風景の一部となり、人々の暮らしに溶け込みながら、豊かな未来を描いている。