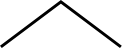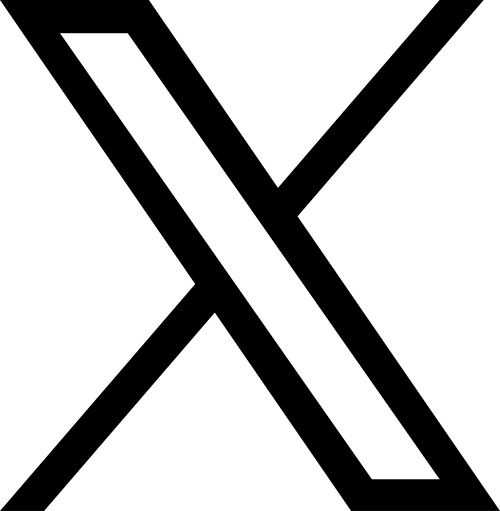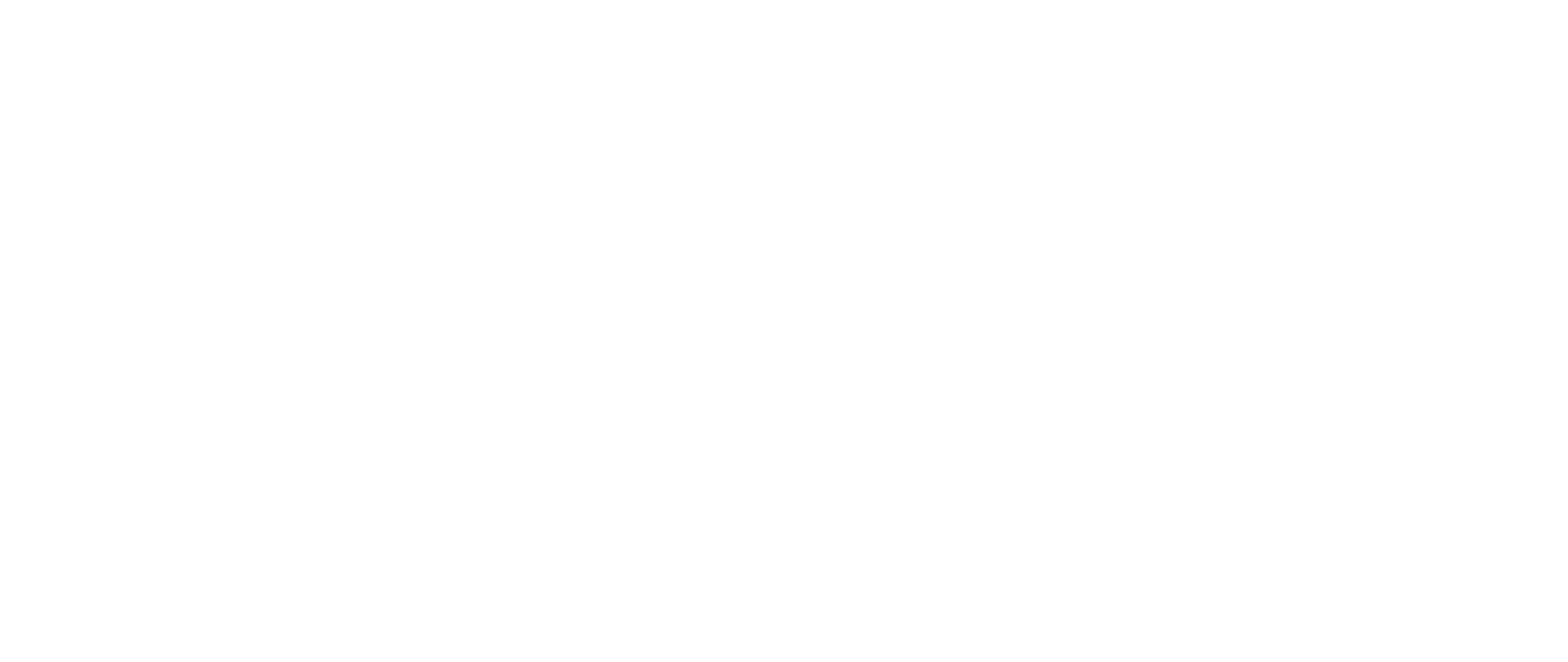知っておきたい動画制作における重要な用語集【ソニーマーケティング×CURBON「撮りたい映像」を形に vol.6】
2024年11月より実施中の、ソニーのデジタルカメラやオーディオ製品などの販売を行うソニーマーケティング株式会社と、写真の学び場『CURBON+』や出張撮影サービス『Creators Base』を運営する株式会社CURBONによる動画クリエイター育成講座『映像制作を仕事に。基礎から学べる育成プログラム』。
今回は、動画制作・編集において頻出する重要な用語についての解説をお届け。なかでも、カラー調整や映像データの圧縮・出力といった、品質に直結する要素を中心に、6つの主要な用語と、それにまつわる考え方や関連する語句を詳しく解説していく。
1:カラーグレーディング(Color Grading)
カラーグレーディングとは動画の雰囲気や世界観を演出するために、色味や明るさ、コントラストなどを調整して作品の「ルック(映像が放つ空気や世界観)」を作る作業です。

【カラーコレクション(Color Correction)】
ホワイトバランスのズレを直したり、明るさを適正レベルに調整したり、映像の「色の正しさ」を整える作業。動画の色を「修正」する。
【カラーグレーディング(Color Grading)】
動画の印象や空気感を作る作業。一部の色味を変えたり、全編通してのトーンの統一をして作品としての表現を高める行為。色で動画を「演出」する。
【LUT(Look Up Table)】
LUTは撮影条件に基づいた、ログガンマで撮影された動画を特定の色味とコントラストに変換できるツールです。各メーカーからログガンマの撮影素材をノーマライズ(ログ撮影のフラットな動画を自然な明るさ・コントラストに戻す処理)するものやある映画のルックを模したものや、一部の色が変わる演色用のものなど、さまざまあり、DaVinci Resolveで自分で作ることもできます。
ただ、LUTは編集用のプリセットではなく、あくまでRGBの変換表となっているためLUTが作られた時と同じカメラ、同じ撮影設定。明るさでないと厳密に再現されません。それが販売・配布されているLUTを自分が撮影した素材に当てても、イメージ通りにならない理由です。


2:エンコード(Encoding)
エンコードとは、動画データを圧縮・変換して、再生しやすい形に書き出す処理です。
編集を終えた映像をそのまま書き出すとそのままではファイルサイズが大きすぎたり、再生機器でスムーズに再生できかったりします。特にYou Tubeやスマートフォンでは対応していないものもあります。そこで再生に適した「形式」に変換(エンコード)することが必要になります。
エンコードは要するに「圧縮する」ということです。一般的には高圧縮するとファイルサイズが小さくなり、再生はしやすいですが、圧縮ノイズが出たり、高圧縮ゆえに、編集作業には向いていなかったりします。映像のファイルについて理解をする場合、コンテナフォーマットとコーデックの違いを知る必要があります。
【コンテナフォーマット(ファイルの形式)】
MP4 / MOV / AVI / MKVなど種類があり、映像・音楽・字幕・メタデータを一つのファイルにまとめています。「.mp4」や「mov」という拡張子がコンテナの種類を示しています。
【コーデック(圧縮の種類)】
H.264 / H.265 / ProRes / DNxHR / AV1など種類があり、映像(音声)をどう圧縮するかを決める技術です。ファイルサイズや画質、編集のしやすさに直結することになります。
※例として「H.264形式で圧縮された映像・AACの音声」が「MP4」ファイルに格納されている、というような構造になるため、なぜmp4でも重くなるのか、MOV全てが高画質ではない、ということが分かると思います。

動画の書き出しは「誰に・どこで見てもらうか」で設定が変わります。今の時代「高画質=正解」ではありません。保存用に高画質版(ProRes のMOV)、共有・アップロード用に(H.264のmp4)など2種類書き出すのも良いでしょう。次項で説明するビットレートも考慮に入れて、最適な設定で書き出しましょう。
3:ビットレート(Bit Rate)
動画の書き出しやYou Tubeなどにアップロードをする際、出てくる「ビットレート」についてです。ビットレートは「動画データの1秒間の情報量」を表す指標です。単位はMbpsです。
基本の考え方として
・ビットレートが高いほど画質はよくなる(細部まで綺麗に見える)
・ビットレートが高いとファイルサイズが大きくなる
・ビットレートが低すぎると、ブロックノイズや色のにじみが出やすくなる
つまり、画質と容量のバランスを取ることが重要となります。ただそ、元の素材が高画質でないものはいくらビットレートを上げても綺麗になりません。
動画配信サービスの推奨ビットレート
YouTubeやVimeoではHD画質(30/60fps)であれば10~15Mbps、4K画質(30fps/60fps)であれば35~60Mbpsとなっています。迷ったらHDなら10Mbps~、4Kならば30~40Mbpsからスタートするのが理想です。TiKTokやInstagramはもう少し軽いビットレートでも大丈夫なようで4Mbpsくらいが最低ラインの目安となっているようです。
4:フレームレート(Frema Late)
本記事の1回目でもフレームレートについて説明しましたが、違う側面の要素も含めてもう一度説明します。
フレームレートは「動画が1秒間に表示するフレーム(コマ)の数」です。「24fps」は1秒間に24枚の静止画が連続して表示されているという意味です(fps = frames per second)。
フレームレートが高い場合(60fps)
動きが滑らかでリアルに見えます。ゲーム実況・スポーツ中継・Vlogなどに向いています。また24/30fpsのタイムライン上でスローモーションの効果を得たい際に使用します。
フレームレートが普通(30fps)
自然に見えるフレームレートです。テレビやYou Tubeなどで多い、情報・トークコンテンツ向きです。
フレームレートが低い場合(24fps)
わずかなカクつきがあり、それが逆に映画のような雰囲気を生みます。ドラマ、映画、ウェディングなど、非日常な物語性のある映像に最適です。
撮影素材に異なるフレームレートが混在している場合は取り扱いに注意します。例えば24fpsのタイムラインに60fps素材を載せると、滑らかすぎて映画っぽさが消えてしまったりします。
5:モーショングラフィックス(Motion Grapics)
モーショングラフィックスとは、テキスト・図形・アイコンなどの静止画的な要素に編集ソフト上で動きをつけて動画として表現する方法です。テレビ番組のオープニングやYouTubeやCMなどのロゴやタイトルアニメーションなどでよく見かける表現だと思います。
キャラクターが登場する「アニメ」とは違い、情報やメッセージを視覚的に伝えることが目的となります。デザイン+動きで視覚的なインパクトを与えます。
モーショングラフィックスはIllustratorやPhotoshopなどで作った素材をAfterEffectsなどで動かすものが主ですが、タイトルテロップなどを動かす簡単なアニメーションであればPremierやDaVinci Resolve内でも作ることができます。アニメーション制作に欠かせない基本用語を紹介しておきます。
【キーフレーム(keyframe)】
大きさや位置の変化における「始まり」と「終わり」を指定するポイントのこと。
例えば「左から右へ動く文字」を作る時、始まりの位置と時間と終わりの位置の時間、2つのキーフレームを設定することで、その間の動きを自動がで補完してくれます。
【トランスフォーム(Transform)】
位置・回転・拡大縮小・不透明度などの動かすオブジェクトに変化を持たせる数値のパラメータのこと。これに対してキーフレームで変化の数値を入れていくことでアニメーションを作る
【タイミング(Timing)】
アニメーションが起こる「速さ」や「間」のこと。
速すぎると視認できない・遅すぎると間延びするため、アニメーション制作には大切な要素
【イーズイン/イーズアウト(Ease In / Ease Out)】
アニメーション設定した対象物の動きの入りと終わりを「なめらか」にする調整のこと。これを加えることで、機械的な直線的な動きより、自然な動きになる。
イーズイン :動き始めはゆっくり、だんだん速く
イーズアウト:だんだん遅くなって止まる
6:ピーキング(Peaking)
流れとは少し変わって最後に「ピーキング」についてです。おそらく写真撮影をされている方の多くはオートフォーカスで撮影されていると思います。ピーキングはマニュアルフォーカスを使う際にちゃんとピントが合っているか、視覚的にチェックできる機能です。フォーカスが合っている部分にギザギザした縁取りや色月のラインが表示されます。
多くのカメラではピーキングの表示色を選べるようになっています。被写や撮影環境の色と被らない色を選ぶと使いやすいでしょう。注意点としては「細かすぎる被写体には向かない」ということです。例えば木の葉っぱや髪の毛など、ディテールが細かすぎると画面全体フォーカスが合っているように見えてしまうことがあります。
動画撮影では「フォーカスイン・フォーカスアウト」というフォーカスを合わせたり、外していくことで動画の演出として使うことがあります。動画撮影だからこそ、マニュアルフォーカスを使った演出にも挑戦するのをおすすめします。
動画撮影を始める前に意識すべきポイント
動画編集は、ただ映像を並べるだけではなく、「どんな見せ方にするか」「どう伝えるか」を設計する作業でもあります。その中で使われる言葉——シャッタースピード、フレームレート、LUT、ピーキング……ひとつひとつの用語の意味を理解することは、その言葉の奥にある“動画の考え方”を掴むことに繋がります。
知っている言葉が増えると、使える技術も増えます。そしてその技術は、やがて自分の動画に“表現の幅”として返ってくるはずです。
まずは焦らず、ひとつずつ。必要なときに、必要な用語がすっと取り出せるようになれば、編集はもっと楽しく、もっと自由になります。言葉を理解することは、動画を理解することにつながります。この用語集が、あなたの動画づくりの土台となり、その一歩を支えるガイドになれば幸いです。
監修・執筆:鈴木佑介