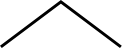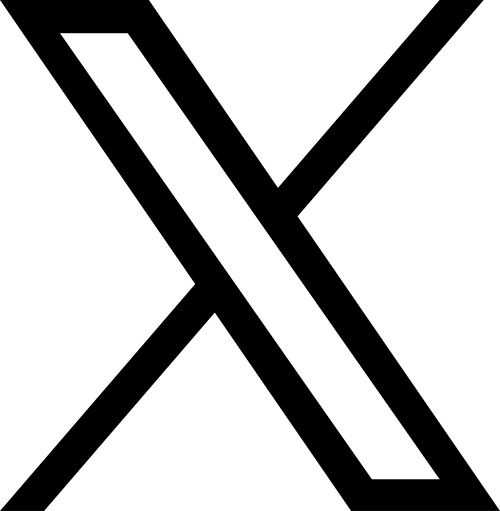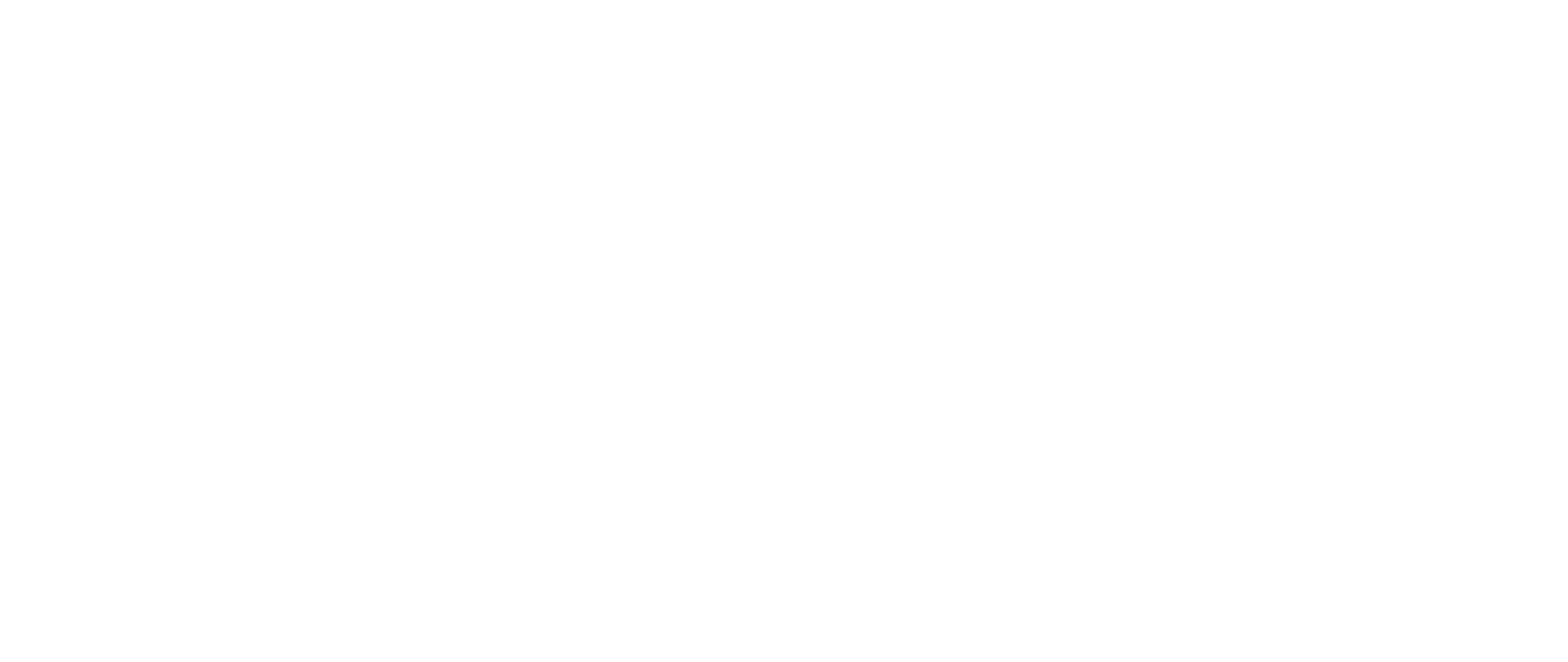変化する映像制作の現場で求められるスキルとは?――ビデオグラファー大川原諒インタビュー【ソニーマーケティング×CURBON「撮りたい映像」を形に vol.3】
2024年11月より実施中の、ソニーのデジタルカメラやオーディオ製品などの販売を行うソニーマーケティング株式会社と、写真の学び場『CURBON+』や出張撮影サービス『Creators Base』を運営する株式会社CURBONによる動画クリエイター育成講座『映像制作を仕事に。基礎から学べる育成プログラム』。
今回は、本プログラムのアドバイザーを務めるビデオグラファー・大川原諒氏へのインタビューを実施。相談会で浮かび上がったフォトグラファーの映像制作における課題や仕事の現場で求められるフォトグラファー像について掘り下げるとともに、ソニーカメラの愛用者でもある大川原氏にその魅力を伺った。
映像制作を仕事に。基礎から学べる育成プログラムとは?
2024年11月からスタートした、ソニーマーケティングとCURBONによる合同プログラム。CURBONの出張撮影サービス『Creators Base』に登録しているフォトグラファーを対象に、3ヶ月のプログラムを通じて映像制作のノウハウを学ぶ内容となっている。 プログラムの最終ゴールは作品課題の提出で、映像制作セミナーやD.O.P/フォトグラファー大川原諒氏による相談会、課題の講評会が行われる。
――まずは相談会のお話を踏まえたうえで、フォトグラファーがムービーを撮る際に陥りがちなこと、直面しがちな課題について改めてお伺いできればと思います。
これまで一枚に重きを置いて撮影してきたぶん、抜きの画でメリハリをつけることに苦戦している人が多い印象です。ムービーの場合はキメ絵とその前後のメリハリをどう作っていくのか、画とストーリーをどう結びつけていくのかという考え方が必要になってきます。目を惹く一枚画を作ることが求められるスチールとは違い、1カットごとのアングルの判断とキメのシーンでどんな演技をしてもらうのかという動画的演出がとくに難しいと感じるところかもしれません。

――スチールにおける演出とムービーにおける演出は、別ものということですね。
たとえば、走ったあとにジャンプをするシーンを撮影するとして、最大の見せ場がジャンプの瞬間だとします。スチールの場合、走り出しの部分は撮りませんよね。ですがムービーの場合は、一歩目の足元の寄りから始まり、ワイドレンズで背後から後ろ姿の腰下くらいまでを追いかけて、ジャンプした瞬間を横からスローで捉えることで、最もエモーショナルな場面を演出します。最初は、そういった撮影のテクニックとピークポイントを作るための演出方法が課題になることが多いように思います。
――そうした課題を克服するためのアプローチや考え方についてもぜひ教えてください。
映像の場合、アプローチの仕方にもかなりの種類があるので、バリエーションを知るという意味ではいろんな映像を観るというのが一番早いと思います。
アングルの決め方でいうと、スチールで撮る場合でいう「キメのアングル」に対して寄り引きをメリハリよくつけてあげるということ。そして、レンズが捉えているのは客観的な視点なのか、それともPOV(ポイント・オブ・ビュー)のような主観視点あるいはなにかモノとしての視点なのかを考えること。カメラがどの視点で被写体を捉えているのかによって、映像から受け取る印象は大きく変わってくるので、そこはすごく重要だと思います。
――大川原さんがムービーを撮影される際は、 なにを基準に視点を決めていらっしゃるのでしょうか?
一概には言えませんが、たとえばシナリオのある対話劇だとしたら、ひとつの会話の中でキーになる言葉を探します。キーのところではしっかりと寄りで見せるけれども、それ以外は2人の立ち位置や場所の説明性を重要視する意味で、空間の演出を取り込んでちょっと引いた画にしてみるとか。CMやWEBの映像を撮影するときはディレクターが別にいることもあるので、提示してもらったポイントは押さえつつ、より効果的な演出や視点を提案するようにしています。逆に、自分の目線で被写体を捉えるドキュメンタリー的な映像は意外とスチールに近い感覚かもしれないですね。

――撮影シチュエーションや映像の狙いに沿って考えていくんですね。
どんな現場でも、とにかく色々な角度から被写体を見るようにしています。スチールでポートレートを撮るときは、シルエットはほぼ使わないと思うのですが、たとえば人物に焦点を当てたムービーの場合、シルエットって意外と効果的な表現方法になったりするんですよね。その他、極端に手元に寄ってみたり、逆にすごく引いてみたり。その場その場で気持ちのいい引きどころがあるとは思うのですが、そうではないところからも探るようにしています。レベルの話をすると普段からスチールを撮っているフォトグラファーって、どうしてもアイレベルでパースを崩さないようにするクセがついていることが多いと思うんですけど、あえて斜めにしてみると(ダッチアングルといいますが)印象的な映像が撮れたりもするので、そこも意識してみるといいんじゃないかなと思います。
――ここまでは撮影者が意識するべきことや考え方について教えていただきましたが、ここからは表現を底上げする機材についてもお伺いしたいと思います。まず、参加者がプログラムで使用するソニー『Cinema Line FX30(以下、FX30)』のアドバンテージはどこにあると捉えていらっしゃいますか?

『Cinema Line FX30』に関しては、APS-Cという意味で利点があります。というのも、フルフレームのシネマカメラを使っていて問題点だと感じるのが、ズーム系レンズの選択肢が少ないこと。ある程度のズーム域をカバーしたいとき、『FX30』であればレンズの選択肢も広がりますし、なおかつフルフレームと同じくらい高精細に撮れるというのは大きな強みだと思います。あとは、別アクセサリーの『FX30』対応ハンドルでは、音声をマイクケーブルで直接入力できますし、ツーミックスされた音源を入力することも可能なので、ライブや舞台のように音響さんと仕事するときにはとくにパフォーマンスを発揮してくれると感じます。
――大川原さんが普段使用されている『Cinema Line FX3(以下、FX3)』と『Cinema Line FX6(以下、FX6)』それぞれの魅力についても教えてください。
まず大きな特徴でいうと、ベース感度を標準の基準感度ISO800と暗所環境用の高感度ISO12800の2つから選択できること。正直使う前は、「ISO12800ってどんなときに使うんだろう」と思っていたのですが、今までライトが必要だった暗い環境でもある程度は問題なく撮れるようになったりと、撮影のしやすさがかなり上がりました。それこそライブ撮影のように照明の関係で明暗差が大きいときに、ISOを12800まで上げておいて、あとは絞りで調整したりすることもあります。『FX6』でいえば「オートND」でコントロールすることもできますし、カメラに任せられることが多くなったというのは現場でも感じている点です。

エンドユーザーは『FX30』や『FX3』、ビデオグラファーは『FX6』、CMや映画ではハイエンド機の『VENICE』と棲み分けこそありますけど、エントリー機にあたる『FX30』や『FX3』はLUTやグレーディング耐性があるという強みがありますし、ソニーは機材のレベル感に格差がないメーカーという印象がありますね。
――せっかく機材のお話が出たのでお伺いしたいのですが、そもそも大川原さんがソニー機を手にしたきっかけとはなんだったのでしょう?
アシスタント時代に、師匠について海外に行く予定があったんです。現地では照明がない蔵の中を撮影することになるかもしれないと聞いていて「持っていける機材も限られているし……」と悩んでいたとき、知人の招待でオープンしたばかりのソニーストア札幌に行ったんですね。そこで、当時発売されたばかりの機種は感度が強いと伺って「これしかないんじゃないか」と思い、購入しました。それで実際に撮影を乗り切ったというのが一番のきっかけでした。

――そこから約8年間、ソニー機を愛用なさっているということですね。
そうですね。もちろん他メーカーのカメラを使うこともありましたけど、メインはずっとソニー機です。機材そのもの優位性はもとより、サポート拠点が多いという安心感も使い続ける理由として大きなポイントです。
――なるほど。ここからは、今現場で求められているビデオグラファー像についてお伺いしたいと思います。ずばり今ビデオグラファーとして活躍するために必要な能力とは?

正直なところ業界は飽和状態ですし、プロと素人の境目がどんどん無くなってきている状況ではあります。その中で、決定的な違いがあるとするならライティングの技術があるかどうかだと思います。どれだけいい機材を使っても、ライティングがダサかったら映えないので。相談会でも「自然光では撮れるけど、ライティングができないからある程度大きい案件になると困る」みたいな声を聞きました。全て照明機材でのライティングが必要というわけではなく照明のコントロールをする力。そういったところでの対応力というのは大きな強みになるんじゃないかなと思います。

――ある程度の機材を揃えてしまえばそれらしい画が撮れてしまうなかで、ライティングのスキルがプロと素人の差別化につながると。
あとは、商品撮りがきちんとできる方やウエディングフォト撮影を長くやられていた方は、スチールを映像に置き換えるだけですぐできることはあると思います。現像ができるところも有利なんじゃないでしょうか。最初は難しいと思うんですけど、現像のスキルをDaVinci Resolveに移行できれば強みになると思います。画としてきれいなものを撮れるのって、やっぱりスチールカメラマンなんですよね。美しく切り取る写真撮影的な視点もうまく活かすことができれば、強力な武器になると思います。

――スチール撮影の表現方法もビデオグラファーとしての強みに変えられるということですね。最後に、今回の参加者に期待すること、映像制作を学ぶうえでのアドバイスをいただけたら嬉しいです。
それぞれの持つ知識やスキルをいい方向で活かせる作品ができあがればいいなと思います。ムービーって、建築写真と同じ撮り方をしていても、抜けの木が揺れていたり人が歩いていたり、そういうところで時間の経過やストーリーが表現されるので、カメラが動かなくても成立するんですよね。普段スチールでガンガン動いて撮影している方だったら、ムービーでも動いていいのかもしれないし、普段どおりの撮影スタイルを落とし込んで、かつその冒頭に話した「抜き」や「間」みたいなものを意識して作れば、ある程度は良いものができるんじゃないかなと。
静物を撮るのが得意な方は、そこの魅力の引き出し方を活かした作品ができると思いますし、すでにフォトグラファーとしてのスキルやセンスといった武器を持ってらっしゃる方たちなので、その武器を最大限ムービーに落とし込んだものが完成することを期待しています。