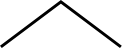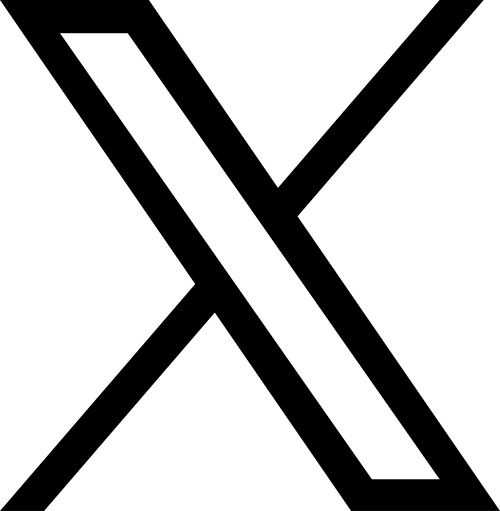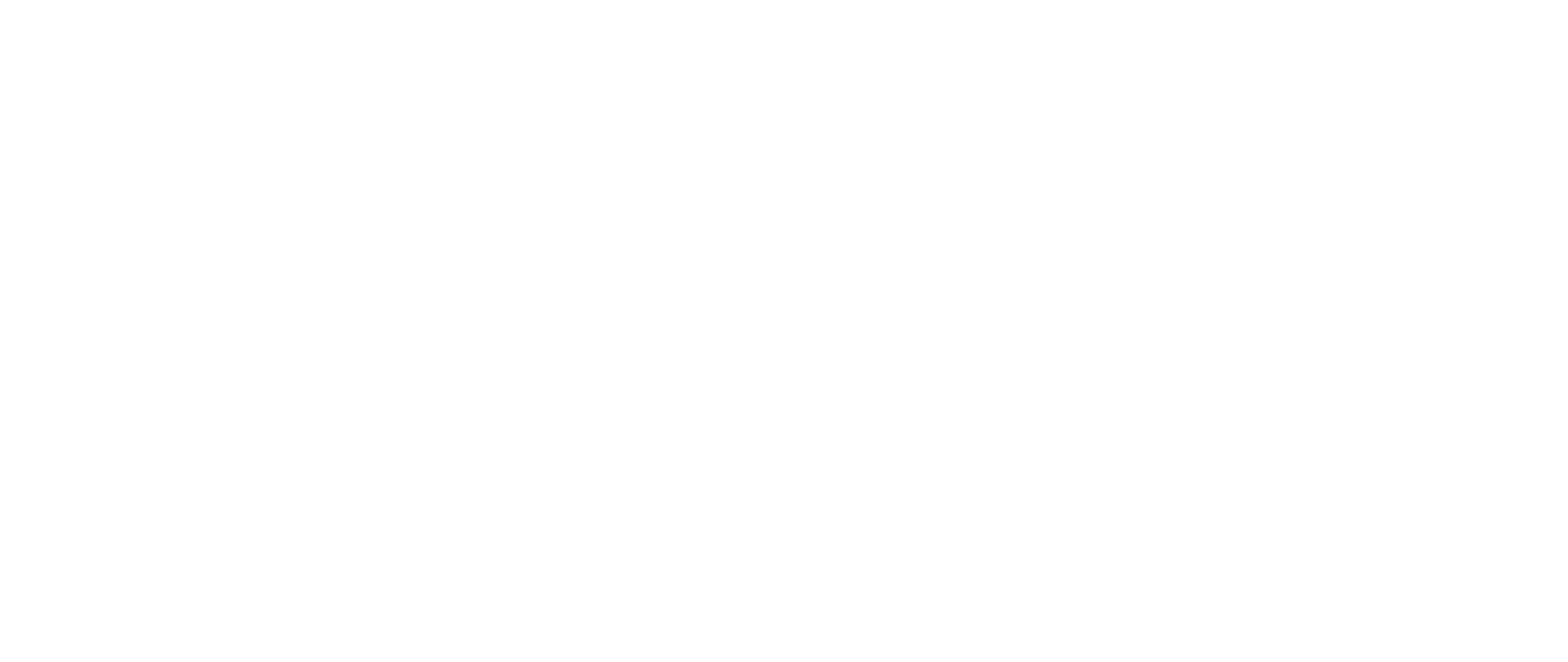映像制作プログラムの集大成!作品講評会〜PART.3〜【ソニーマーケティング×CURBON「撮りたい映像」を形に vol.10】
ソニーマーケティングとCURBONの合同プログラムとして2024年11月からスタートし、CURBONの出張撮影サービス『Creators Base』に登録しているフォトグラファーが3ヶ月間にわたり映像制作のノウハウを学んできた『映像制作を仕事に。基礎から学べる育成プログラム』。その集大成である提出課題作品の講評会が、3月27日(木)に開催されました。
多彩な作品が寄せられた本講評会の内容と、計6作品の概要を2作品ずつ全3回にわたってお届けしてきた本企画。ラストとなる今回は、エンタテインメントの世界で人間の二面性を切り取った意欲作、『everyday(河尻 彩江)』『劇場(伊藤 愛)』の2作品を紹介します。
PART.1・PART2はこちらから
映像制作プログラムの集大成!作品講評会〜PART.1〜
映像制作プログラムの集大成!作品講評会〜PART.2〜
『everyday』河尻 彩江
映像より一部シーンを抜粋(撮影機材:α7 II)
作品コンセプト / 制作者コメント
Ollie wonder time machineさんの楽曲「everyday」のミュージックビデオをつくりました。コンセプトは、「今を生き、今日を愛する」。日常にある幸せも、忘れたいような嫌なことも、全部ひっくるめて生きてほしいと思えるようなことを伝えたいというメッセージを込めました。
日常の中にある感情をわかりやすく表現するための状況づくりや画角の選定、初めての編集作業に苦労しました。演出に関しては、20〜30代前半の方に共感してもらえるように、1人のサラリーマンの1日を描き、自分もこういう場面に遭遇したことがあるなと共感できるようなシーン作りにこだわりました。
映像の尺:3分程度/制作期間:撮影 2日・編集 1週間
大川原氏 講評
3分尺のMVを作るのって私たちでも結構大変なことなので、この短期間で完成させた時点でまず大拍手です。リップシーンが4種類ぐらいあるということからマルチトラック編集は100パーセント入っているので、そのあたりも工夫されていますし、アングルも結構凝っているなと感じました。
音無しで見ていても伝わる部分があるので、構成的はしっかり出来ているなと思う一方で、技術的なところで少し不足を感じる部分がありました。まず、ピクチャープロファイルやログで撮影して、もうちょっとグレーディングで頑張ってみるというところがあってもいいのかなと思います。編集でスローをかけている部分もカメラ側でスロー&クイックを使えたらより良かったのかもしれません。
序盤の俯瞰や足元に寄るシーンのようなバリエーションは良かったのですが、特に歌っているパートは寄りが多いので、日常の彼はもうちょっと他人目線で見せられるとすごくいいのかなとは思いました。たとえば、橋でスマホを見ているシーンは思いっきりカメラ引いて橋にポツンと佇んでいるところを見せたり、逆にお酒を飲み交わしている楽しいシーンは、もうちょっと内に入った目線だったり。訪問のシーンもへこへこしている姿をお客さん側の目線でリアルに見せたり。「誰かから見た彼」の視点があれば、彼の二面性や心情の変化にもう少し寄り添えたのかなというふうに感じています。
全体的にミュージックビデオとしての構成はすごくよく出来ているので、そういったメリハリがつけられるとさらに良くなるかなと思います。
『劇場』伊藤 愛
映像より一部シーンを抜粋
作品コンセプト / 制作者コメント
タイトルは「劇場」です。演劇という生きた表現の世界と、その舞台に立ち続ける俳優の姿を残すことをテーマに、この作品を見た人が劇場に足を運びたくなるようなものにしたいなと思って考えました。と同時に、今回の作品は俳優の、映っている手嶋 萌さんの記録でもあるので、ドキュメンタリー的な要素も組み込んで映像を作りたいというところを大切に、演劇と映像の可能性を探るというのが、私の中ではすごく大きなテーマのひとつでした。
苦労した点は、カラグレと照明の設計です。カラグレについては、1つのシーンだけでなく、写真と違うのが、カットごとの統一感とか、全体の流れを考慮しながら、細かい調節を重ねる必要があったのが、すごく難しかったです。手持ちカメラの微妙な揺れを活かして舞台の息遣いや緊張感をリアルを切り取り、固定した状態でカメラを構えることで、役者の動きを際立たせるという演出も調整しました。
映像の尺:◯秒程度/制作期間:撮影 1日・編集 3日
大川原氏 講評
映像としてはすごくいいなと感じました。俳優が醸し出している雰囲気というのを全体通してすごく感じられましたし、表情をはっきりと映さないぶん、もう少し見てみたい、ナマの演劇を体験してみたいと思わせる余白が生まれていたと思います。ただ逆に、たとえば手先とか口元だけとか目元だけとかに逆にもうすごくクローズした寄りがあっても良かったかもしれません。
制作についてのコメントを聞いたうえで映像を見た時に、俳優のドキュメンタリー的なところはありつつも、演劇そのもののプロモーションにはちょっと繋がりにくいのかなというところを少し感じました。音楽の歌詞なり雰囲気をフォローするミュージックビデオの特性と、人の本質を映し出していくドキュメント性と演劇そのものの訴求という3つのコンテンツがあるが故に、どこに落ち着いたらいいのかなというのが10数回見たうえで感じていることです。
正解は僕もわからないのですが、最後の最後に晴れ舞台が映るとか、葛藤や迷いといったネガティブに見えてしまいそうな部分を何らかの形で明るく回収するという必要はあるのかなというふうに思いました。もしドキュメンタリーに寄り添うのだとしたらオンとオフの姿、ポジとネガみたいなギャップがあるといいのかなと思います。
画の捉え方しかり、空間の捉え方しかり、それに伴う色や光のニュアンスも、慣れていないながらにすごくいい方向にいっていると思います。今後もしこういう作品づくりのを続けていかれるのであれば、30秒ぐらいのソーシャルコンテンツとしていろんな俳優さんを捉えていくものをつくったら、良いコンテンツになるんじゃないかなと思いました。
映像文化のさらなる発展を願って

約5ヶ月間にわたり実施された本プログラム。今回初めて動画制作にチャレンジしたという参加者も多数いるなか、「一人で1から学ぶよりも圧倒的に効率よく、正しい知識を得られた」、「スチールと映像との違いを面白さとして捉えることが出来てるので今後もどんな形であれ映像制作をしていきたい」といった、映像制作についての学びや楽しさを実感したという声を聴くことができました。
普段フォトグラファーとして活動する参加者にとっては、シネマカメラの使用も新鮮な体験であり大きなチャレンジだったそう。今回のプログラムで貸与されたFX30についても「とても軽くて扱いやすく、APS-Cなので被写界深度が深く使いやすい」、「軽量なのに本格的な撮影が可能であり、操作もしやすい。撮影時に複数箇所で赤く点灯するので、撮り逃しも無い。長時間の撮影でも高温で止まる心配が少なく、安心して使用できた」など、実施期間で培われた技術と機材への信頼がうかがえる感想が多数寄せられました。
アドバイザーを務め、参加者とのコミュニケーションを通してプログラムの進捗を見つめてきた大川原氏は、今回の講評会を終え、こう言葉を寄せました。
「もともとクリエイターとして活動されているみなさんのそれぞれの目線や色が映像にも出ていたのがまず良かったかなと思っています。私自身も写真からムービーに移った人間なので、『わからないということが、わからない』という時期がすごくありました。今はノウハウをわかりやすく発信されている方もいたり、カメラもどんどん進化していろんなことがコンシューマーで出来るようにもなってきているので、いろんな映像を見て、なぜこうなっているんだろうと考えながら、それを自分の持っているカメラでどう実現するかというトライアンドエラーを重ねていくことができれば、少しずつ実力が向上していくんじゃないかなと思っています」
そして、大川原氏と同様に実施から本プログラムを支えてきたソニーマーケティング・堀氏は、講評会を感謝と期待の言葉で締めくくりました。
「こうした取り組みをさせていただくのは初めてだったので、至らない部分もあったと思うのですが、みなさん最後まで仕上げていただいて本当にありがとうございます。世の中、市場の動きを見ていても、動画広告やSNS広告はどんどん増えています。フォトグラファーとして活動されている方も動画の案件が増えてきているというのは感じているところのかなと思うので、スチールと動画を合わせてやっていくというチャレンジはぜひ続けてほしいなと思います。
今後もソニーでは動画系のイベントを実施していきます。我々からもサポートさせていただきながら、皆さんと一緒に映像文化を育てていけたらなというふうに思っていますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします」
———
今回の講評会を持って修了となった動画クリエイター育成講座『映像制作を仕事に。基礎から学べる育成プログラム』。今回のプログラムを通じて、フォトグラファーとしてのスキルに加え、新たな映像表現の可能性を学んだ参加者の方々が習得した知識や技術が、今後活動の幅を広げ、映像文化のさらなる発展につながることを願っています。