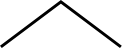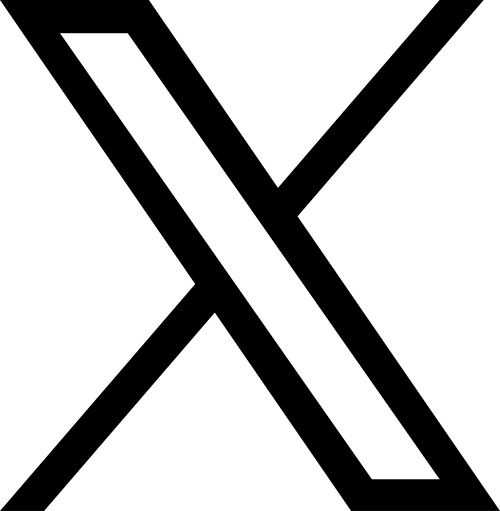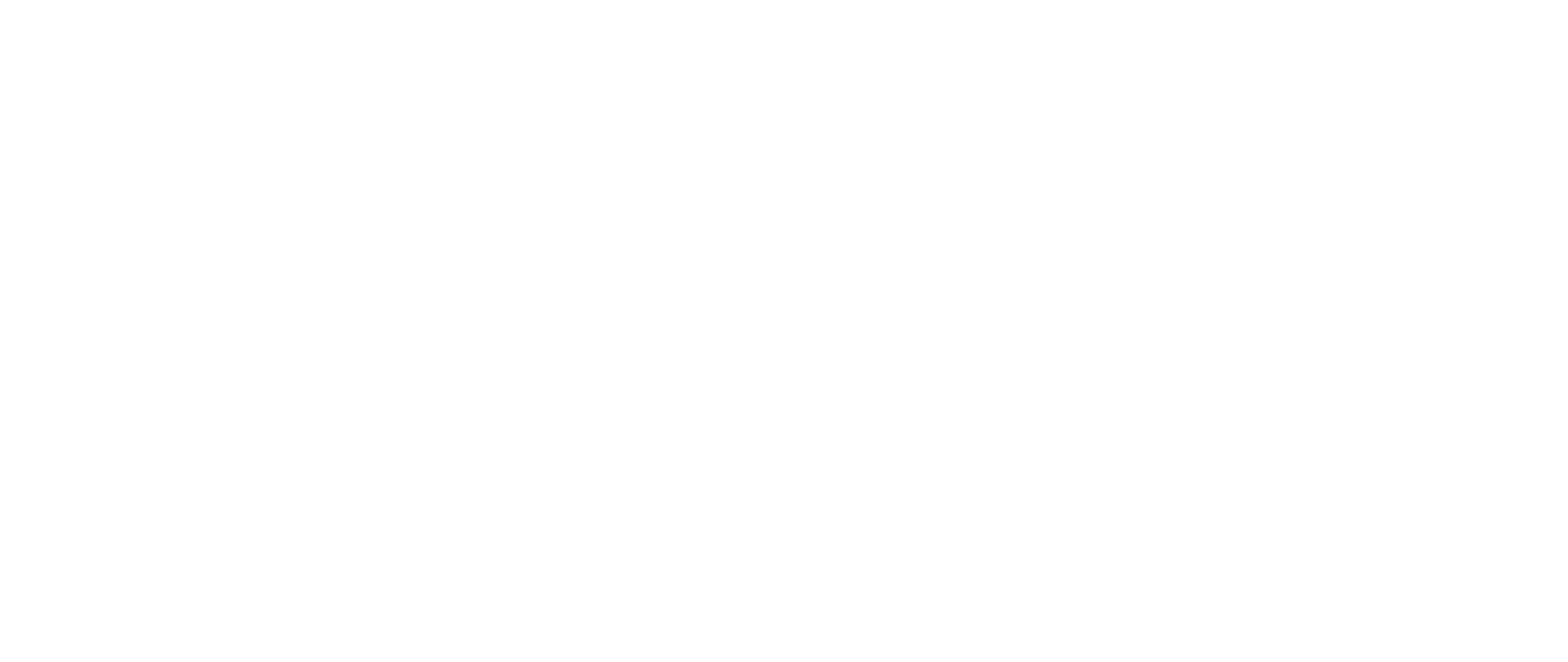映画『ミーツ・ザ・ワールド』監督・松居大悟インタビュー「人はそれぞれ違うからこそ、愛おしい存在だ」
2025年10月24日(金)に、全国公開される映画『ミーツ・ザ・ワールド』。
第35回柴田錬三郎賞を受賞した金原ひとみの同名小説を、監督・松居大悟が映画化。主演・杉咲花をはじめ、南琴奈、板垣李光人、蒼井優、渋川清彦ら実力派キャストが集結した本作は、歌舞伎町を舞台とした新たな出会いが導く世界を描いた物語です。

あらすじ
擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」に全力で愛を注ぎながらも、自分のことは好きになれない由嘉里。27歳になって結婚・出産…と違う世界に次々と離脱する腐女子仲間をみて、このまま仕事と趣味だけで生きていくことへの不安と焦りを感じ、婚活を始める。しかし参加した合コンで惨敗。歌舞伎町で酔いつぶれていたところ、希死念慮を抱えるキャバ嬢・ライに助けられる。
ライになぜか惹かれた由嘉里は、そのままルームシェアを始めることに。やがて、既婚のNo.1ホスト・アサヒ、人の死ばかりを題材にする毒舌作家・ユキ、街に寄り添うBARのマスター・オシンと出会い、歌舞伎町での生活に安らぎを覚えていく。そんな日々の中でもライのことが気がかりな由嘉里は、かつての恋人との確執が解ければ死にたい感情は消えるかもしれないと考え、アサヒやユキ、オシンに相談する。だが、価値観を押し付けるのはよくないと言われてしまう。それでもライに生きてほしいと願う由嘉里は、元恋人との再会を試みるが―。
▶︎予告編はこちらから
監督を務めたのは、映画『ちょっと思い出しただけ』など、青春の一瞬の輝きを描き続け、若者から圧倒的な支持を得る松居大悟。本作で、初めて「生きること」そのものをテーマとして描いた彼に、制作にまつわるエピソードから作品に込めた想いについてお話しを伺いました。
PROFILE

PROFILE
松居大悟 Daigo Matsui
1985年11月2日生まれ、福岡県出身。劇団ゴジゲン主宰。2012年『アフロ田中』で長編初監督。『ワンダフルワールドエンド』(15)でベルリン国際映画祭出品。その後、『私たちのハァハァ』(15)、『アズミ・ハルコは行方不明』(16)、『アイスと雨音』(18)、『くれなずめ』(21)、テレビ東京系列「バイプレイヤーズ」(17〜21)シリーズ、『リライト』(25)など。『ちょっと思い出しただけ』(22)で東京国際映画祭にて観客賞・スペシャルメンション受賞。『手』(22)でロッテルダム国際映画祭に正式出品するなど、枠にとらわれない作風は国内外から評価が高い。
「居場所のなさ」をやわらげられる映画を
ーー最初に原作を読んだとき、どのような印象を受けましたか。
登場人物たちが、曖昧で掴みきれない感情を繊細に言語化していて、心理描写の細やかさやセリフの勢いに圧倒されました。夢中で読み進めるうちに、自分もこの世界に入りたいと思ったほどです。
特に、ライの一つひとつの言葉が達観していて、いいセリフだなと何度も思いました。なかでも、「別の時代だったり別の国だったら変わる物差しで自分を測るの?」という言葉が強く印象に残っています。今の社会って、みんながそれぞれ狭い世界の中で「こうした方がいい」と言い合っていて、自分が見てきた範囲だけで他人を判断してしまうことが多い気がします。
周りの評価に左右されることの多い今の時代だからこそ、本当は誰もが面白いものや独自の視点を持っているはずなのに、それを上手く使えている人は意外と少ない。僕自身、そこをもどかしく感じていたので、とても心に残りました。

ーーこの作品を映画にしたいと思われたのは、原作のどのようなところに惹かれたからでしょうか。
金原さんの作品は、どれも興味深く読んでいたのですが、自分とは少し距離のある人物ーー今回で言えば、ライのような存在を主人公に立てていて、自分が映画を撮るという発想はなかったんです。
でもこの作品では、由嘉里という人物を通してライを見つめるという構造に惹かれました。由嘉里がライを「どうにかしたい」「守りたい」と思う気持ちが印象的で。舞台である歌舞伎町や、そこに生きる若い人たちの「息のしづらさ」「居場所のなさ」のようなものを少しでもやわらげられるのでは……という想いから、この映画を制作したいと感じました。

ーー今回、初めて「生きること」そのものをテーマとした作品に挑まれたそうですが、難しいと感じた点はありますでしょうか。
この映画では、「価値観が違ったまま寄り添っていこう」という思いを抱えて作っていたのですが、でも、「寄り添おう」というメッセージ自体が、もしかしたら誰かの生き方を否定してしまうかもしれないとも感じて。その矛盾とどう向き合うべきかには、とても悩みました。
ーー主人公・由嘉里役のキャスティングはどのように決められたのでしょうか。
原作を読んだときに、主人公・由嘉里の姿が杉咲花さんで浮かんできたんです。直前にドラマ『杉咲花の撮休』でご一緒していたこともあってか、「杉咲さん以外はない」と思うぐらい鮮明にイメージできました。
今回の映画のプロデューサーも、「由嘉里の姿を杉咲さんに当てて小説を読んだ」と言っていて。それで自然と、杉咲さんに演じてもらおうという流れになりました。

ーーキャバ嬢・ライ役はオーディションで決められたそうですね。
はい。初めは由嘉里と同世代の20代後半の女優さんを想定していましたが、あまりイメージが湧かなくて。これからの人に出会いたいと思い、オーディションを行うことにしました。

沢山の応募者の中から最終的に3人に絞り、杉咲さんにも最終オーディションに立ち会っていただきました。その際、杉咲さんが南琴奈さんと芝居をしたときだけ、思わずセリフを飛ばしてしまったんです。「南さんと目の前で芝居してたら、セリフが抜けてしまった」と言っていて。
その言葉が由嘉里とライを表してる気がして、「これはもう南さんしかいない」と感じました。当時、彼女は高校2年生で、とても印象的な出会いでした。
役者自身が生み出すものを映画で描きたい
ーー作品を撮るうえでこだわった点について教えてください。
由嘉里とライのまったく違う価値観や考え方を映画でどう表現するか考えるなかで、由嘉里の「ライさんと私は肺呼吸とえら呼吸ぐらい世界が違うんです」というセリフが心に残っていて。台本を組み立てながら、”水”が大きなテーマになると考えました。
雨上がりの歌舞伎町での出会いや水たまり、バーのシーン、回収されない水槽、水の溜まった灰皿など、さまざまな場面で水をモチーフとして使うことで、由嘉里にとっての世界の見え方や距離感について表せたらと。特にライの化粧を落とすシーンなどはどうやって見せるか、みんなで悩みました。

ーーキャストやスタッフのみなさんとのコミュニケーションで工夫した点について教えてください。
毎回の撮影でもそうですが、「決めつけない、固めすぎない」ことを意識しました。もちろん役者さんはプロなので、指示をすればやってくれますが、それよりも、役者さん自身が役や背景を捉えて生み出すものを映画で描きたいと思っているんです。だから、役者さんが提案や相談してきてくださるものを最大限取り入れるようにしています。

例えば、由嘉里とお母さんが話し合うシビアなシーンはかなり相談を重ねました。由嘉里はお母さんを見たくないので目線をあまり合わせず、でもお母さんは由嘉里のことが心配だから、由嘉里がポイっと投げたものを拾ったり、畳んだりする。そうして最終的に距離が近づくけれど、結局由嘉里が逃げるようにして出ていってしまう。そのときのお母さんの言葉が、由嘉里に刺さる。
この一幕で、由嘉里が何を感じて、どのように立ち去るかなどは、特に相談し合いながら作りました。

ーー特に印象に残っている撮影シーンはありますか。
由嘉里のデート相手・奥山譲を演じた令和ロマンのくるまさんの撮影シーンは特に印象に残っています。奥山譲は、くるまさんが演じるのを見てみたいと思い、今回オファーしたんです。
撮影前、くるまさんが「セリフをちゃんとセリフとして言うと恥ずかしいし、失敗してるように見えるのも嫌だから、語尾を少し崩したりしちゃうかもしれないですけど、ニュアンスは変わらないようにするんで、もし離れすぎてたら言ってください」とおっしゃってて、すごく映画に対して寄り添ってくれる方だなと思いました。

韓国料理屋での由嘉里と奥山のデートシーンは、芝居中にアニメの音声が重なってきて、アニメの声で奥山の声が聞こえなくなるという特殊な撮影だったので、アニメが喋り続けてる限り奥山はセリフがなくても喋り続けなきゃいけなかったんです。でもくるまさんは、戸惑うことなくずっと喋り続けてくれて。その対応力を見て、本当にすごいなと感心しました。
丁寧な世界観づくりで、観客を物語へ引き込む
ーー主人公・由嘉里がこよなく愛する擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」のアニメ制作もされたそうですね。
はい、もともと映画や舞台を中心にやってきたので、アニメの作り方はまったくわかりませんでした。ただ、原作には「擬人化焼肉漫画」のような面白い要素があって、それを愛しているファンもいるからこそ、かなり説得力のあるアニメにしなければと思って。

原作には世界観や設定がほとんど書かれていなかったので、まず「学園ものにしよう」と決め、キャラクターの人数や性格、口癖、名ゼリフなどをアニメ監督であるUWAN深瀬さんやデザイナーさんと細かく作り込みました。そこから3分~5分のショートアニメの台本を脚本の國吉さんに書いてもらい、さらにコンテの作成や、作画やオープニング曲の制作まで関わりました。結果的にアニメ完成まで約1年かかり、映画1本分に匹敵するくらいの体力を使ったので、とても大変でしたね。
ーー推し活を表現するなかで意識したことはありますか。
二次創作を愛していて、推し活をされている方々にお会いして、実際に話を伺いました。
例えば、池袋で集合してアニメイトやKーBOOKSなどをどういうコースで巡るのかを一緒に体験したり、グッズの重要性について聞いたり、いい絵師の方の作品を見たときの反応を見たり。
人によって推し活のスタイルはさまざまで、すごく喋る人もいれば静かに楽しむ人もいる。そこから「由嘉里は誰に近いのか」と想像しながら、世界観や人物像の解像度を上げていきました。

ーー推し活シーンで出てくるグッズなど、世界観づくりでこだわった点について教えてください。
7頭身のアクスタや2頭身のSDキャラなどを用意し、さらにコラボカラオケのシーン用に部活設定のコスプレをしたキャラクターの作画も行いました。「痛バ(推しキャラのグッズを詰め込んだバッグ)」は、推し活をされているみなさんが持っていたこともあり、絶対に出したかったので、ぬいぐるみタイプや缶バッチタイプなど、種類ごとに制作していきましたね。
衣装や服装も細かい部分までイメージを固めていたのですが、演出部や美術装飾チームのプロフェッショナルな仕事のおかげで、思っている以上のものに仕上がりました。

ーー今回の作品への想いや、観客のみなさまに特に注目してほしい点がありましたら教えてください。
近年の風潮として、人々が考え方の違いを否定し合い、息苦しさを感じることが増えていると感じます。SNSによってそれが可視化され、心が傷つくことも多い。でも、この映画を通して、「人はそれぞれ違ってもいいし、だからこそ愛おしい存在だ」ということが伝われば嬉しいです。
▼information
映画『ミーツ・ザ・ワールド』
【公開日】2025年10月24日(金)全国公開
【出演】杉咲花、南琴奈 、板垣李光人、蒼井優、渋川清彦、筒井真理子、くるま(令和ロマン) 、加藤千尋、 和田光沙、 安藤裕子、 中山祐一朗 、佐藤寛太
(劇中アニメ「ミート・イズ・マイン」) 村瀬歩、 坂田将吾、 阿座上洋平 、田丸篤志
【監督】松居大悟
【脚本】國吉咲貴、 松居大悟
【原作】金原ひとみ『ミーツ・ザ・ワールド』(集英社文庫 刊)
【配給】クロックワークス
©金原ひとみ/集英社・映画「ミーツ・ザ・ワールド」製作委員会
Text&Edit:田畑 咲也菜