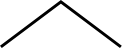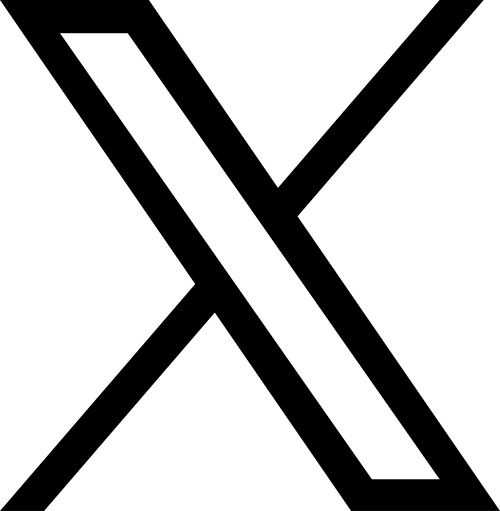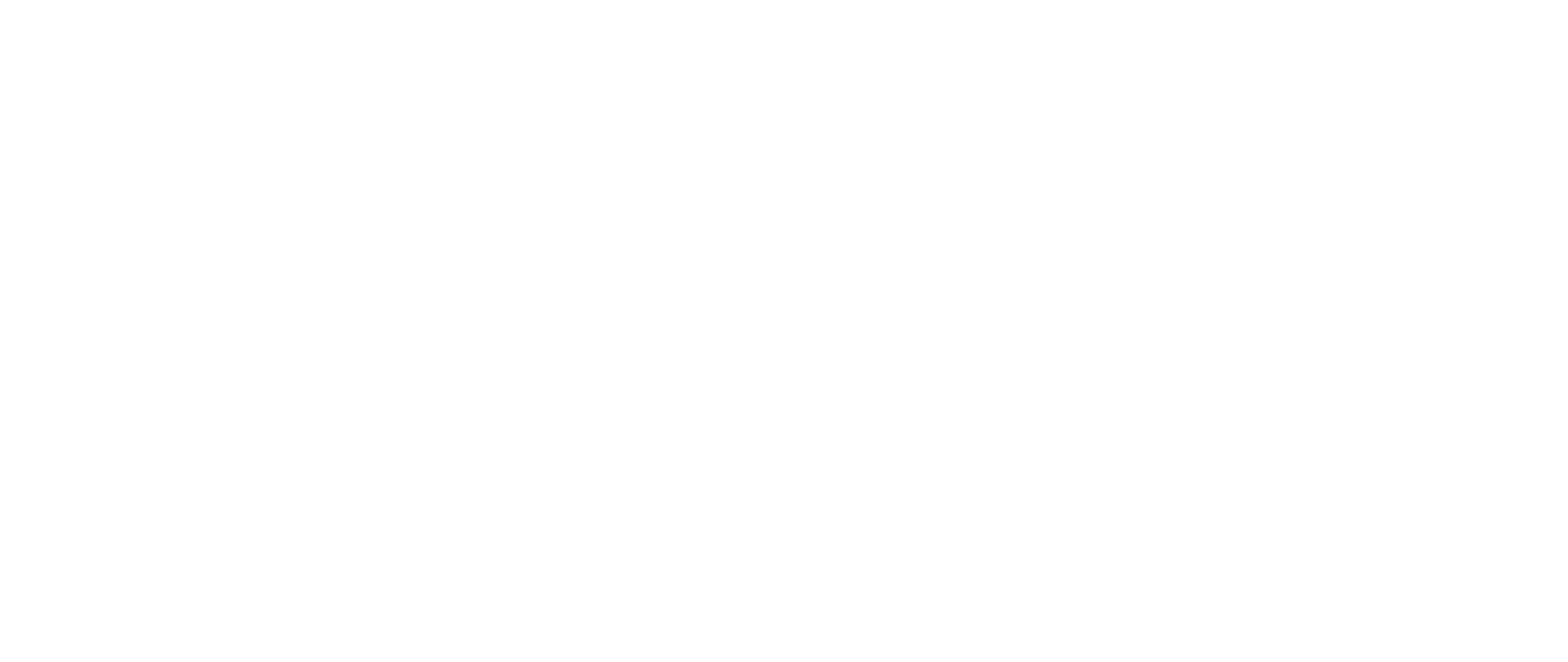写真祭「SEEEU ヨーロッパ写真月間 2025」– 文で読む写真展
「耳で聴く美術館」を主宰するaviさんによる、フォトアートを自身の言葉で綴る連載「文で読む写真展」。今回も、aviさんが写真の奥にひそむ物語を、静かにひもといてゆく。
PROFILE

PROFILE
avi / 耳で聴く美術館
美術紹介動画クリエイター。1992年大阪府生まれ。「心が震えるアートの話をしよう」をテーマに、動画プラットフォームを起点にアートの魅力を紹介。大学で美術教育を学び、教員資格も持つ。キャッチーな表現とわかりやすい解説、柔らかなCalmボイスで急激にフォロワーを伸ばし、アートの間口を広げた。現在抱えるフォロワー数は50万人を超える(2025年3月時点)。
@mimibi_art301 https://www.mimibi.ch/10月の終わりの月曜日。
六本木の朝はちょっと湿り気があり、そびえ立つ六本木ヒルズは、この街を守る砦のよう。
風が冷たくなると街の鮮度が上がる気がするのは私だけだろうか?
今回私が訪れたのは今年初開催の写真祭「SEEEU ヨーロッパ写真月間 2025」。
14名の現代写真家の作品が、東京各地の屋内・屋外会場で無料公開される。

はじめに私が訪れたのは、都営バス「EXシアター六本木」バス停前(渋谷方面)工事仮囲いにある『Taiyo Onorato & Nico Krebs: Water Column』。スイス出身の2人の写真家による作品だ。
アフリカ大陸とアラビア半島にはさまれた紅海で、写真家たちが自ら潜って撮影したというこの作品。サンゴの群生やクラゲなどの深海生物などが、水中で幽玄な生命力を放つ様子を捉えている。

私が気に入ったのはこちらの作品。
まるで桜吹雪を真下から眺めているような華やかさだ。海の中なのにね。

そして、こちらの作品も好き。
こちらは構図が『風神雷神図屏風』の様に見えて面白かった。

私が取材用にパシャパシャ写真撮影していると、道ゆく人が「なんだ?なんだ?」とつられて写真作品を見る。
この方々がもし普段写真展や美術展に行かない人だったのだとしたら、この写真祭には、鑑賞するという行為を0→1にする力があると思った。
工事現場の警備員さんや巡回中の警察官の方、スーツを着て出勤している方や、子供を後ろに乗せて自転車を漕ぐ女性が、ちらっと紅海の生物たちを見ていく。果たして六本木の街を行き交う人々は、それぞれの生活の狭間で遠いヨーロッパの海の底の生物たちを見て、なにを思ったのだろうか。



EUはヨーロッパ連合といい、フランスやドイツ、イタリア、スペインなど、ヨーロッパの国々が参加していると、中学生の頃に習った気がする。
遠い地球の向こう側で撮られた写真たちが、東京の街に染み込むように馴染んでいる。
それは “東京”という街が、なんでも飲み込む巨大な生物のような街だからなのかもしれない。

次の会場へはタクシーで向かう。
東京の街を知るには車移動が面白い。
路線図に縛られないので、地名どうしの位置関係や、道のつながり方などの地理感覚がついてくる。
ビルが森のように連なっていて、私が生まれた街とは比べ物にならない大都会。
私はこの街が好きだ。
だから、この街が会場になるのはとても嬉しい。

到着したのは新宿。
WPÜ SHINJUKUというホテルの一部でIgor Schiller: Familiar Characters という作品を見ることができる。こちらの会場は屋内で鉄骨が組まれている中に電球が吊り下げられていて、展示空間にも造形美を感じられた。

作者のイーゴル・シラーはセルビアとオランダを拠点に活動している写真家。
「大人になった今だからこそ、生まれ育った環境や文化を客観的に見つめ、子ども時代の感覚を理解したい」と、生まれ育った土地から離れて暮らしていたシラーが、故郷セルビアに帰郷し3年間をかけて撮影を行ったらしい。
作品には、ぞくっとするのにどこか惹きつけられもするような、夜のサーカスの様な印象を受けた。

この写真の男性がまたがっているRODYをみて懐かしい気持ちになる。
うちの実家にもこの赤いRODYちゃんがいて、小さい頃に乗って爆走していたなと。
けれど、大人サイズで見ると若干の恐怖を覚えるのはなんでだろう。

また、このうさぎたちの部屋の写真。
入ったら、そっと扉を閉めて見なかったことにしたくなる気持ちはなぜだろう。
そんなことを考えていた。

写真祭で展示されているEUの街並みをみてふと思う。
中学生の頃、教科書で見たEUの国々に行くんだろうなと思っていたが、何年経ってもその兆しがない。
これを機に行ってみようかなという気持ちが0→1になった。きっかけって大切だな。

今回の写真祭は、東京の街のなかに散りばめられた写真が、例えばふとその場所を訪れた通行人にも目に入るように設計されている。
歩いているとふと、写真作品が現れるのはいい。
歩きながら見ていると、構えることなく作品を見つめることができる。それはホワイトキューブで作品を見る感覚とは異なる。美術館に行くと、チケットを買って荷物を預けて、いざ作品とご対面という背筋が伸びる感覚になるが、今回の写真祭の作品との対峙の仕方は「いきなり!ステーキ」ならぬ、「いきなり!写真展」だ。
こんな思わぬタイミングでの作品と人々の出会いを、私も発信で作れたらな〜と思わされる。
会場を抜けて、たくさんの車とたくさんの観光客で賑わう新宿三丁目の方へ歩いて行った。
私も、この街に溶け込める様になったかな。
文:耳で聴く美術館 avi
編:並木 一史