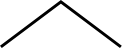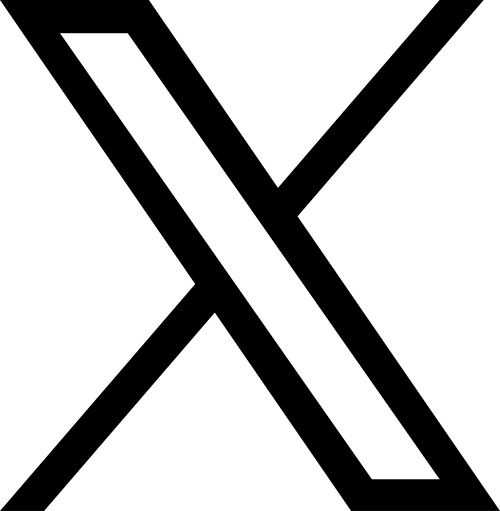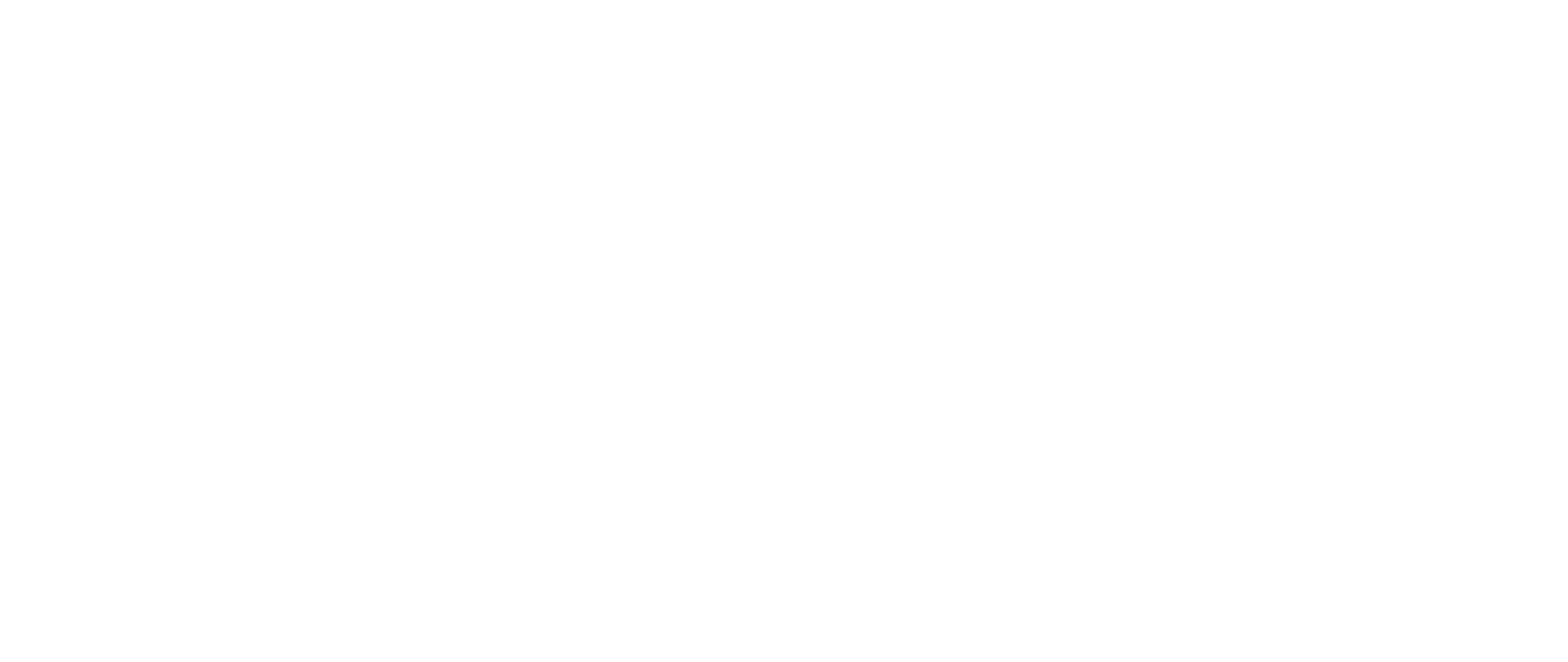「新聞を配ることは気を配ること」- 山陰中央新報社の広告制作の舞台裏
新聞配達員の日々の営みに焦点を当て、地域社会における新聞の役割を再考させた、山陰中央新報社の「新聞を配ることは、気を配ること。」キャンペーン。
本プロジェクトは、地方新聞社の課題解決に向けた広告制作の取り組みとして注目を集め、全国の消費者が選んだ広告コンクールでグランプリを受賞するなど、高い評価を得た。

本記事では、広告キャンペーンの企画から実施に至るまでのプロセスを、クリエイティブチームの生の声とともにお届けする。
Creative Team Profile
PROFILE
PROFILE
原正樹
山陰中央新報社 読者局読者部(現:総務局人事総務部)。創業140周年を迎えた山陰中央新報社において、新聞配達員の確保や育成に関する課題に取り組む。本プロジェクトの企画立案者。
PROFILE
PROFILE
日下 慶太
コピーライター・写真家・コンタクティ。1976年大阪生まれ、大阪在住。コピーライターとして働きながら写真家、UFOを呼ぶためのバンド「エンバーン」のリーダーとしても活動中。商店街のユニークなポスターを制作しまちおこしにつなげる「商店街ポスター展」の仕かけ人。著作に自伝的エッセイ『迷子のコピーライター』(イーストプレス)、写真集『隙ある風景』(私家版 )。佐治敬三賞、グッドデザイン賞、TCC最高新人賞、KYOTOGRAPHY DELTA award、造本装幀コンクール日本印刷業連合会会長賞、ほか受賞多数。
PROFILE
PROFILE
布野カツヒデ
株式会社あしたの為のDesign 代表取締役。島根県出雲市出身。印刷会社、デザイン事務所勤務を経て、デザイン会社「株式会社あしたの為のDesign」設立。島根広告賞大賞。公益社団法人 全日本広告連盟(全広連) 鈴木三郎助地域キャンペーン大賞 選考委員会特別賞。第60回 JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール 新聞部門 JAA賞グランプリなど受賞多数。島根県を拠点に活動するグラフィックデザイナー。地域に根ざしたデザインワークを展開。
新聞業界が抱える課題を解決するために
── 新聞を作る人に焦点を当てた、この広告の制作背景について教えてください。
原正樹(以下、原):地方において、人口減少や高齢化が進む中で、新聞業界にも様々な課題が生じています。特に若い新聞配達員の確保が難しくなってきており、高齢な配達員の割合が高いんですね。体調を崩されたり怪我をされたりすると、代わりに配達してくれる人が見つからない集落もあります。こうした現実に、私たちの会社も例外なく課題を感じていました。
そんな状況の中で、2022年に会社の140周年という節目の年を迎え、各部署がそれぞれ大型企画をスタートしていました。その中で、私が所属していた読者局では、新聞配達員にスポットライトを当てた自社広告企画を始めることにしました。
「彼らが日々どのように仕事に向き合っているのかを、読者の方々に知ってもらえるようなプロモーションを行いたい」そう考えた背景には、配達員の皆さんが抱える課題や、業界全体が直面している問題を少しでも解決するために、何か新しい取り組みを始めたいという想いがありました。
新聞配達のスタッフたちが誇りを持てる広告をつくる
── 新聞各社が抱える課題と背景のもと、広告制作にあたって、どのような方針で臨まれましたか?
日下 慶太(以下、日下):言葉や広告で価値を転換して、新聞配達のスタッフにも誇りを持ってもらいたいと考えました。キャッチコピーの名作、大成建設「地図に残る仕事」は、建築業界は「3K」(きつい、汚い、危険)というイメージが根強く、若い世代から敬遠されがちでした。そうしたなかで、このキャッチコピーを掲げました。この言葉が、現場の作業員たちに自分たちの仕事への誇りを取り戻させたんです。「俺たちの仕事は地図に残るんだ」と感じることで、建設業のイメージを変えた。
同じように、ディズニーランドでは清掃員も「キャスト」と呼ばれていますよね。清掃という仕事にも誇りを持たせ、スタッフ全員が物語の一員、主人公であるという意識づけがある。
まずはそんな思いを胸に、実際に現場で働く人に話を聞いてみることにしました。
「早く取材終わってほしいな」からスタートした制作の舞台裏
── 「毎日が障害物競走。」の配達員のおばあさんの広告、最高でした。当たり前のように新聞が配達される日常に感謝できるような、そんな気づきを与えてくれる広告でしたが、どんな舞台裏だったのでしょうか。
日下:実際に取材や撮影を始めた当初、ある配達員のおばあさんは「なんで私のところに取材に来るんよ、早く取材終わらんかな」と思っていたようで、全然心を開いてくれませんでした。配達の話を少し聞いてみても、「そんな話すことないわ」という様子が見え隠れしていました。少し距離があったんですね。
とはいえ、実際の仕事ぶりや、撮影のロケ地も決めなくてはいけないので「配達コースを一緒に回らせてくれませんか?」とお願いしました。布野さんが運転して、おばあさん(光岡さん)は助手席に座り、車でぐるっと回ることになりました。
車が1台通れるか通れないほどの細い道だったり、車を降りて急な山道を歩いたりと、すごい配達コースでした。布野さんが「配達は本当に大変ですね」と言ったんです。すると、おばあさんが「そうじゃろ」と答えて、急に心を開き始めたんです。
布野カツヒデ(以下、布野):まさにその瞬間が、すごく印象的でした(笑)。
日下:そこからは、どんどんお話ししてくれるようになり、だんだんとおばあさんの心が開いていったんです。その後、写真を撮ることにしたんですが、おばあさんが綺麗なエプロンを着てくれて、すごく素敵な姿を見せてくれました。
布野:それまでの緊張感が和らいだ瞬間でした。実際に回ってみると、その道の大変さや、朝早くから働いている人たちの苦労がよくわかり、あのおばあさんの素敵な一面を見られたように思います。
「新聞を配ることは、気を配ること。」はどのように生まれたか
── 「新聞を配ることは気を配ること」というコピーはどのように生まれたのでしょうか?
日下:配達員のことを聞けば聞くほど、新聞配達の仕事をしているスタッフたちが、どれだけ気を配っているかに改めて気づきまして。
新聞がポストに溜まっていると、不在にしているのか?新聞が取れないような異変があったのか?と心配をしたり、知らない車が止まっているとか、いつもは電気が点いていないのに点いているとか、周囲の異変に気を配っています。
他にも、ポストに落とすか、ポストに挟んだままか、というような細かいところも、配達員の皆さんが決めているんですよ。例えばある一軒家では、ポストの中に入れると、犬がいるので、犬が新聞をぐちゃぐちゃにしてしまうから、挟んだままにして配達しています。別の場所では、挟んで落とした方が良い場合もあったりします。いろいろなケースがあって、そういうことを覚えているんです。
日下:それから、同じ時間に配達するというのも大切なことです。少しでも時間が超過してしまうと、生活のリズムに影響が出るんです。朝食を食べながら新聞を読むという人がいるので、ちょっとでも遅れたら、「あれ、今日は遅いな」と思われてしまうんですね。届け先にいる人の時間に合わせて配達している。そんな話を聞いたとき、すごいなと思いました。配達のプロフェッショナルで、新聞配達ということを通して、読者に気を配っている、という価値が浮かび上がってきたんです。
裏テーマは山陰の広告。島根らしい風景を切り取った
── コピーだけでなく、ビジュアルも美しいです。なおかつ少し暗い雰囲気の画が多く、撮影も苦労されたのではないかと想像します。撮影で特にこだわり抜いた点について教えてください。
布野:やっぱりロケ地には徹底的にこだわりましたよね。本当に、ロケ地選びは慎重に行いました。
日下:実際、何ヶ所も見に行きましたし、かなり遠くまで足を運んだんです。新聞広告として採用していない場所もたくさんありますが、それでも本当に恵まれたロケーションが揃っていました。
布野:山陰らしい風景を切り取ることができたのが、本当によかったです。特に印象に残っているのは、ポストに新聞を投函している配達員さんのシーンですね。小薮の細い道を進んで、こっちに何か家があるのかな、というような場所に差し掛かりました。すると、急に景色が開けて、こんな風に広がっているんですよ。
布野:奥にはおそらく、ご夫婦が住んでいらっしゃるお家があり、そのご夫婦は90歳ぐらいのお年を召した方々でした。もう、その家の周りは草刈りがきちんとされていて、すごく整った感じがありました。とても丁寧に生活されているなと感じました。何というか、とても落ち着いていて、良い場所だなと思わせてくれるような、そんな雰囲気が漂っていました。心が温かくなるような場所だったんです。
実際、新聞が発行された後、そのご家族の家に再度訪ねていったんですけど、そしたら、新聞が額に入れられて家の中に飾ってあったんですよ。それを見たとき、すごく嬉しい気持ちになりました。
ご夫婦も、うちの家がすごくきれいに紹介されているのを見て、すごく嬉しいとおっしゃってくださって。その言葉を聞いた時、心に感じるものがありました。
地域社会の課題を解決するところまで考え、広告を届ける
── 広告の反響はいかがでしたか?
原:「本当にやってよかったな」と思う瞬間が、いろんな場面であります。日下さんと布野さんと、一緒に素晴らしい広告を作ることができたことにすごく感謝しています。
当初は配達員さんや読者の方々に何を届けるべきかという点で悩んだ部分もありましたが、読者の方からは「これを見て、配達員をやってみようと思った」という声が寄せられたり、「辞めようかと思ったけどもう少し続けてみるよ」と言っていただいた配達員の方もおられたようで、本プロジェクトの意義を感じることができました。
読者の方から日々の配達に対する感謝のお手紙もいただけました。その手紙には、新聞がどのように届けられているのかを知り、深く感動したというメッセージが込められていました。これも、私たちにとって非常に嬉しいことでした。
日下:クリエイティブな仕事を通して、課題を解決するのはやりがいがありますし、何より面白い。山陰の良いところは、会社の課題が社会課題としっかり結びついている点なんです。だいたいの案件は商品が売れないとか、認知度やブランドのイメージが良くないとか、そういった課題なんですが、山陰は社会の問題に繋がっていることが多いので、やりがいが大きいんですね。
一番大きな課題は、新聞配達員がいなくなることで「新聞」という地域のライフラインが止まってしまうことです。あわせて、配達の際にさりげなく行われていた独居のご老人への見守りの機会も失われてしまうのは、大きな懸念点です。そういう社会課題を解決できるのが広告の仕事。意義があるし、楽しいし、やりがいを感じています。
広告は、誇りを醸成する仕事
今回のプロジェクトは、地方新聞社が抱える「新聞配達員の確保難」という課題に対し、広告を通じてクリエイティブにアプローチした一例だ。
新聞配達という、日々の生活に欠かせない当たり前の営みに新たな価値を見出し、その努力と感謝を表現したことが、配達員の誇りを高め、読者の理解を深める結果に繋がった。
広告のつくり手は、どうしても目の前の「売る」ことに意識が向きやすい。モノやサービスを売るためのツールだと捉えている作り手も多いだろう。
しかし本来、広告には、社会の中で見過ごされがちな営みや存在に光を当て、人々の意識を変えていく力がある。
課題の解決に向けて、どんな視点で社会に向き合い、どんなビジュアルやメッセージを届けるのか。
誰の仕事や想いに寄り添い、その価値を届けるのか。
それらもまた、広告の制作に携わる人に求められる大切な視点ではないだろうか。
写真提供:山陰中央新報社