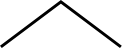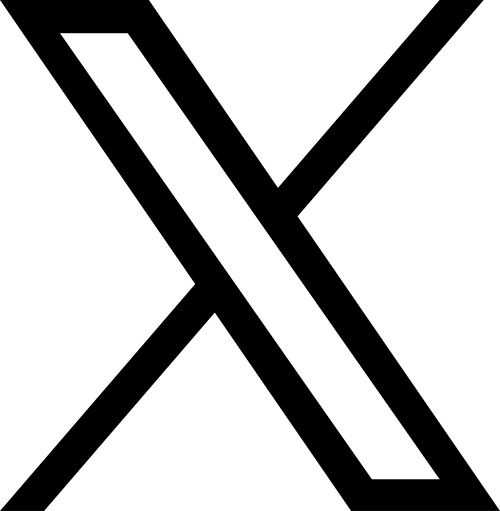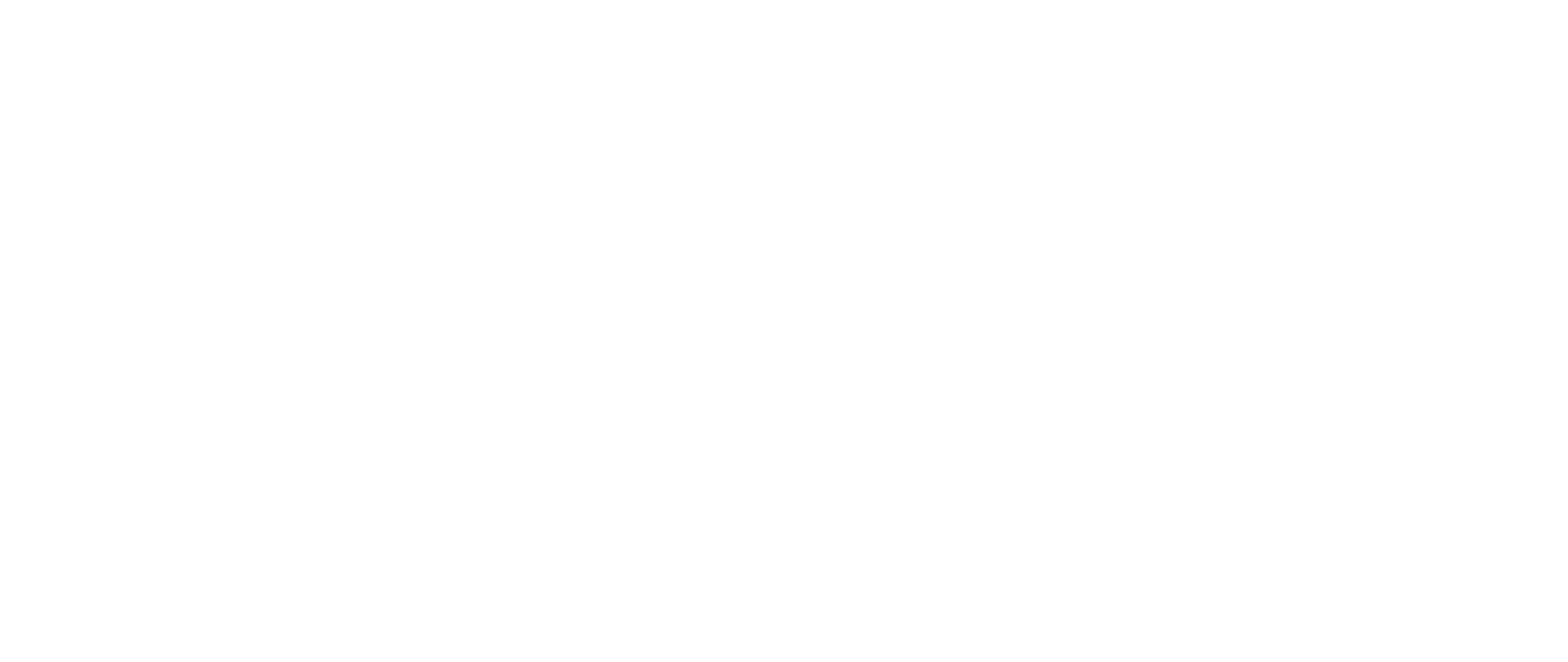《連載記念インタビュー》”心が震えるアート”を届ける「耳で聴く美術館」。活動の始まりと、これから描く未来のこと
「心が震えるアートの話をしよう」をコンセプトに、「耳で聴く美術館」の活動を展開する動画クリエイターのaviさん。展示情報や作品解説をわかりやすく伝える彼女の動画は、多くの人々の心を掴み、SNSを通じて世界中にアートの魅力を届けています。
そんな「耳で聴く美術館」の連載企画「文で読む写真展」が、2025年4月からスタート。連載開始を記念して、aviさんに活動をはじめたきっかけやアートへの思い、これから挑戦してみたいことについて、お話を伺いました。
PROFILE

PROFILE
avi / 耳で聴く美術館
美術紹介動画クリエイター。1992年大阪府生まれ。「心が震えるアートの話をしよう」をテーマに、動画プラットフォームを起点にアートの魅力を紹介。大学で美術教育を学び、教員資格も持つ。キャッチーな表現とわかりやすい解説、柔らかなCalmボイスで急激にフォロワーを伸ばし、アートの間口を広げた。現在抱えるフォロワー数は50万人を超える(2025年3月時点)。
@mimibi_art301 https://www.mimibi.ch/美術特有の“寄せつけなさ”を取っ払いたかった
ーー「耳で聴く美術館」の活動を始めたきっかけについて教えてください。
大学生の頃、美術系の学科に通っていたのですが、そこで学ぶうちに、「アートって、思っていたほどハードルが高くないんだ」ということに気づきました。でも同時に、こんなことも思ったんです。「美術を楽しむことって、外から見るとなんだか近寄りがたい雰囲気があるよな」って。
たとえば、専門的な知識がないからという理由で、美術館に行くのを躊躇したり、SNSでアートの感想を気軽に発信できなかったり。そういう状況ってすごくもったいないな、と心のどこかで感じていました。それが、活動の原点になっていますね。
転機となったのは、2021年のコロナ禍です。家で過ごす時間が増え、TikTokを眺めているうちに、「自分もSNSで発信してみようかな」と思いました。誰でも気軽にアクセスできる媒体でアートについて話すことで、美術特有の“寄せつけなさ”を少しでも取り除けるんじゃないかと。そんな想いから「耳で聴く美術館」として活動を始めることにしました。

ーーたしかに。日本人にとって美術は少しハードルが高いイメージがあるかもしれません。
たぶん、私たちの日常生活と美術との距離が少し遠いんだと思います。たとえば、フランスだと、スーパーの袋を持ったおばちゃんが、気軽にギャラリーに立ち寄って、作品をパーっと見て帰っていくんだそうです。それを聞いて、向こうではアート作品がもっと身近なものになっているんだな、と感じました。
アートの楽しみ方は、人の数だけあっていい。
ーー「耳で聴く美術館」は、aviさんの優しい語り口が印象的ですね。この発信スタイルを選んだ理由について教えてください。
実は私、幼い頃からラジオっ子で、情報を得るときに、視覚よりも聴覚からの方が頭に入ってきやすいタイプなんです。小説も、読むより聴く方がイメージが膨らみやすくて。
Instagramは、写真だけの投稿もできますけど、ショート動画だと音声もつけられますよね。それなら、視聴者さんの耳からアートの魅力を伝えたいなと思って、話しかけるような形式を選びました。
ーー活動を続けていくなかで、「手応えを感じる瞬間」はありますか?
動画を見てくださった方が実際にアクションを起こしてくれたり、展示会や作品の広がりに貢献できたときに「やっていてよかった」と感じます。
たとえば、数年前になりますが、会期終了まで3日というタイミングで、ある展示の投稿をしたところ、残りの日数で一気に来場者数が増えたらしいんです。
あとは、作品を紹介した動画が、数日で400万回ほど再生されたこともありました。海外の方々からのリポストが相次ぎ、それを見た人がまた共有してくれて、思いがけないバズを生んだんです。
日本の小さなギャラリーで展示されている作家の作品が、一瞬で世界中に広がっていく。たった一つの投稿でこれほどの影響力を持てることにとても驚きましたし、大きなやりがいを感じました。
ーーたしかに、SNSの投稿をきっかけで、美術館に足を運ぶ人が増えているように感じます。それについて、どのように感じていますか?
そうですね。SNSの影響力のおかげで、ふだん美術館に足を運ばないような人たちにまで、アートが届くようになったと感じます。それは、本当に嬉しいことだなと。
ただ、たまに「美術館に行ってきました」という投稿に対して「美術館ではなく、美術館に来ている私を楽しんでいますよね」といった批判的なコメントを目にすることもあって。そういった反応を見ると、悲しい気持ちになりますね。
美術の楽しみ方って、人それぞれだと思うんです。写真を撮りたくなるほど作品に魅力を感じた人もいれば、記念写真をきっかけに作品をもっと知りたくなる人もいる。それなのに、多様な楽しみ方を否定してしまうことで、美術館に行くのを躊躇う人が増えてしまうんじゃないかと。それでは本末転倒ですよね。美術の鑑賞方法は、人の数だけあっていいと思っています。
ーーちなみに、aviさんが作品と向き合うときに、大切にしていることは何ですか?
ファーストインプレッションを大切にしていますね。作品が生まれた背景や芸術的な価値などは後から確認するようにして、まずは自分自身の感想を持つことを心がけています。
作品と解説が並んでいると、つい解説を読んでから作品を見てしまいがちです。解説を読むと作品をしっかり理解できた気になりますが、それをぐっと我慢して、作品そのものと向き合う時間を作るんです。筆のタッチとか絵の具の重なり方とか、そういったものを先入観なしで観察すると、自然と自分なりの感想が生まれてきます。

といいつつ私も、映画を見た後は、すぐにレビューサイトで他の人の感想を見てしまうんですけどね(笑)。これってきっと、映画にあまり詳しくないことへの不安からだと思います。
美術でも不安を感じると、解説を読みたくなることもありますが、インフルエンサーとして発信するうえで、自分の感想を伝えることは大切にしたいですし、作品を純粋に楽しむ気持ちも忘れたくないな、と。
写真が映し出す現実は、物事を多面的に捉えさせてくれる
ーー写真とアートの違いについて、どのように考えていますか?
絵画関連の展示会情報に触れる機会が多いこともあり、写真展にはあまり足を運んだことがないんです。私が写真作品を目にするのは、主に美術館に訪れたとき。絵画や彫刻作品と並んで、展示された作品を見ることが多いですね。そのせいか、写真とアートは別の畑のものだと感じたことはほとんどありません。
ただ、写真作品は、どこか荒削りな感じでヒリヒリするというか、見ていると現実を突きつけられるような感覚がありますね。目を背けたくなるような作品は、絵画や彫刻よりも写真に多いように感じます。それは、私たちの生きている世界を、ありのままに映し出しているからなのかもしれません。
ーーこれまで見た写真作品の中で、印象に残っているものはありますか?
2024年に、国立新美術館で開催された展覧会「遠距離現在」で見た、ティナ・エングホフの孤独死をテーマにした作品が印象に残っています。
この作品は、デンマークで孤独死された方々の生年月日や発見された場所、日付とともに、その方が亡くなった後の家の写真が展示されているんです。そこにはもう誰もいないはずなのに、ベッドに座っていた跡が残っていたり、クローゼットに今まで着ていた服がかかっていたり。そこで生活していた人の存在を強く感じられて、胸が締めつけられる作品でした。
デンマークというと、社会福祉が整った「幸せな国」というイメージがあったんです。でもこの作品をきっかけに、デンマークの人たちの強い自立精神が、かえって他人に頼ることを難しくしていて、それが人との繋がりを希薄にしているという側面を知りました。
私自身、「社会福祉=幸せ」という、あまりにも一面的な見方をしていたことに気づかされましたね。これは、写真だからこそ伝えられるリアルだなと思います。
ーー連載「文で読む写真展」で、写真展を巡ることについてはどう感じていますか。
私は、美術という分野で活動していますが、実は専門分野があるわけではないんです。「耳で聴く美術館」の活動においても、古美術などの知らない分野に「学ばせていただく」気持ちで飛び込むようにしていて、そこで得た学びを皆さんに共有したいという思いで、動画を制作しています。
だから今回の連載を通じて、写真についてもっと深く学んでみたいですね。報道写真からアート性の高い作品まで、写真にもさまざまな形があると思うので、規模やジャンルに捉われず、いろいろな作品を見ていきたいです。
連載を通じて、ふだん写真展に足を運ばない方々にも「写真展に行ってみよう」と思っていただけるようなきっかけを提供できれば嬉しいですね。
ーーさまざまな活動に精力的に取り組まれているaviさんですが、最後に「耳で聴く美術館」として、これから取り組んでいきたいことを教えてください。
同世代の作家さんたちの活動を盛り上げるお手伝いをしたいと考えています。
最近では、作家さんたちを動画で紹介することに加えて、アーティストアーカイブサイト「こんにちは!アーティストさん」を立ち上げました。このサイトでは、さまざまな作家さんの想いや経歴、作品を見ることができます。

立ち上げた背景としては、次の世代に向けて、今を生きる作家さんたちの活動を記録として残していきたいと思ったからですね。
というのも、SNSは瞬間的に注目を集められますが、数年経つと動画のレコメンドも減って、次第に見られなくなっていきます。それってすごくもったいないし寂しいことだなと。
そこで、SNSでの活動と並行して、SNSに依存しないウェブサイトも地道に作っていこうと考えたんです。同世代の作家さんの作品や想いを、しっかりと伝えていける場所を用意したいなと。
まずは、活動を通じて出会った作家さんたちにお声がけをして、掲載いただいた作家さんたちの力になっていきたいと思っています。まだまだ小さな動きですが、これから少しずつ大きな輪になっていったら嬉しいです。
***
アートの魅力を多くの人に発信するとともに、次世代に向けた取り組みにも力を入れている「耳で聴く美術館」のaviさん。彼女が写真展に赴き、そこで感じたことを文章で紡ぐ連載「文で読む写真展」が4月からスタートします。ぜひお楽しみに。
Text&Edit:しばた れいな