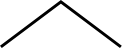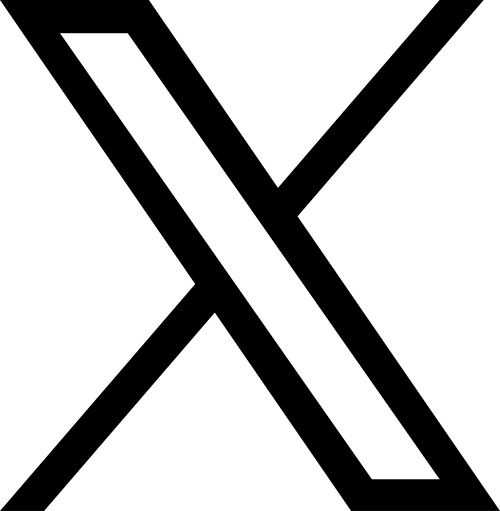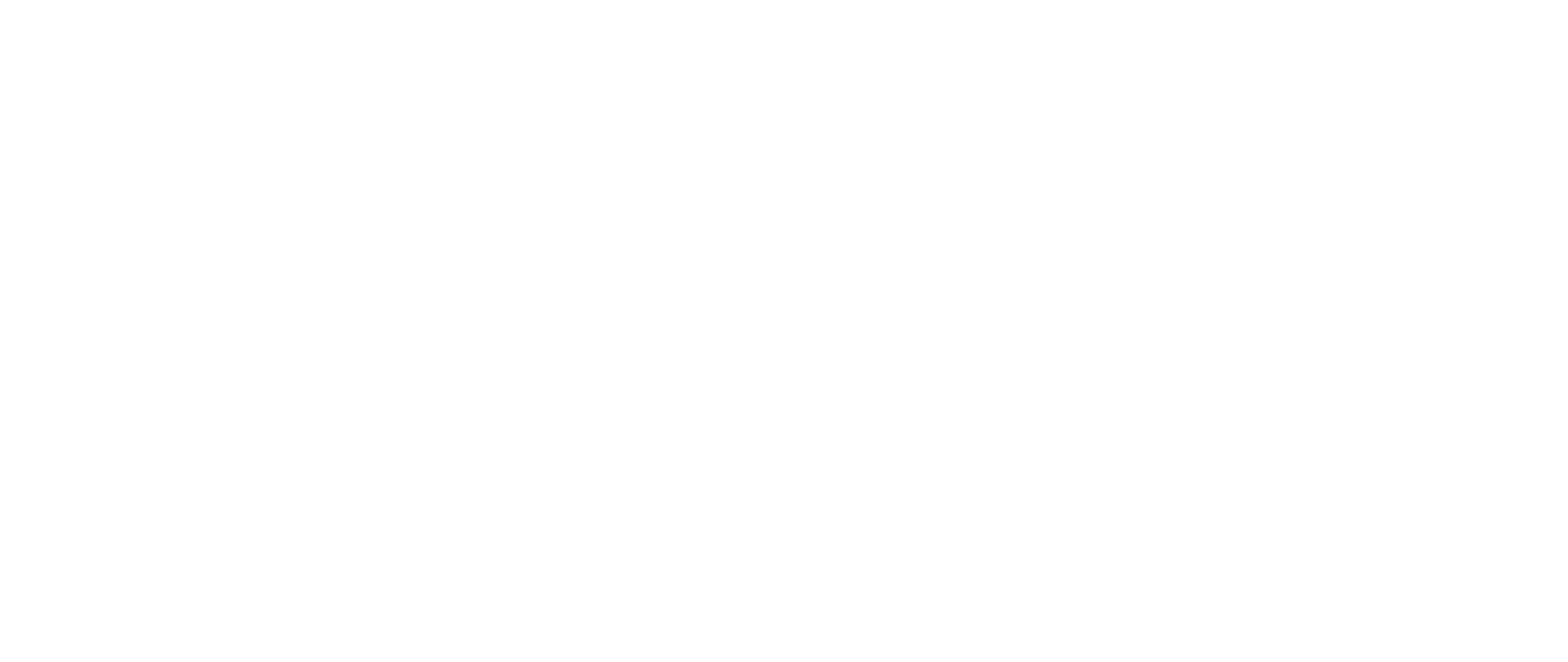「これまでに観たことのないタイトルバックをつくる」『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』制作陣が語る舞台裏
2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。そのオープニングを飾るタイトルバックは、視聴者の目と心を一瞬で引き込む映像表現だと話題を呼んでいます。
演出を担当したのは、NHKディレクターの深川貴志さん。映像表現の中核を担ったのは、クリエイターのTAKCOMさんと、アニメーションディレクターの石志哲郎さん。そして現場全体をまとめあげたのが、プロデューサーの増田悠希さんです。
深川さんが掲げたのは「これまでにないタイトルバックをつくりたい」という提案でした。静的な映像が多かった大河ドラマの慣例に対し、コラージュや静止画アニメーション、3Dなど多様な技法を組み合わせることで、まったく新しい表現に挑んだのです。
浮世絵、実写、手描きアニメ、3Dといった異なる手法を行き来しながら、何度も調整を重ねて完成した映像。その背景には、蔦屋重三郎という人物さながらの、人を巻き込み遊び心を発揮する力が宿っていました。この映像が生まれるまでの物語を、4名の言葉からひも解いていきます。
▼タイトルバックの映像をご覧になりたい方はこちら
YouTube:大河ドラマ『べらぼう』タイトルバック
PROFILE
PROFILE
深川 貴志(演出/NHKディレクター)
『麒麟がくる』『おんな城主 直虎』『カムカムエヴリバディ』『らんまん』などを手がけてきたNHKディレクター。今回のタイトルバックでは、「江戸と現代は地続きである」というコンセプトと、「渦(うず)」というビジュアルの中心軸を提示した。当初はコラージュという手法に「情報過多で無機質になるのでは」と懸念もあったが、TAKCOM監督のスタイルフレームを見て、その世界観に惚れ込む。実写素材とアニメーション、エキストラの撮影など、NHK局内外との調整役も担いながら、演出チームとして全体のバランスをとっていった。
「制作チームそのものが“渦”の中で、蔦重のように人を巻き込んで世に届けるエンタメの入口を作っている。そんな実感のある仕事でした。」
PROFILE
PROFILE
増田 悠希(プロデューサー)
映像・グラフィック・Webなど多様な媒体をプロデュースしてきた。『カムカムエヴリバディ』の朝ドラOPで深川ディレクターとタッグを組んだ経験を持つ。タイトルバックで使用したコラージュ手法については、「神田の古書街に立つと江戸を感じるように、過去と現在がまざりあう感覚を表現したかった」と語る。チームが安心して創作できるように調整を重ねながら、納品直前まで細やかな調整にもスピード対応。制作者たちのやりたいを実現するプロデューサーとしての姿勢が光った。
「大河の枠組みの中でも、ここまでやれるんだという挑戦を形にしたかった。」
PROFILE
PROFILE
TAKCOM(監督・映像作家)
映像ディレクター・アートディレクターとして活躍。映画「花と雨」やドラマ「RoOT」の監督脚本、大阪・関西万博の開会式パフォーマンスでの映像や、パビリオンでのPerfumeのオープニング映像なども手掛け、ジャンルに縛られず実験的な表現を手がけてきた。今回の『べらぼう』では、単なる切り貼りではない“シームレスで構造が見えない”コラージュを目指し、CG、実写、手描きアニメ、印刷物のような質感などを緻密にブレンド。横浜流星の表情演出から素材選定、演出コンテ作成、テンポ調整に至るまで、多岐にわたるプロセスにこだわりを持って臨んだ。
「歴史がいまにつながっているその実感を視覚的に届けられた、理想的な仕事でした。」
PROFILE
PROFILE
石志哲郎(アニメーションディレクター)
映像制作会社「Liki」代表。広告映像やミュージックビデオなどを手がけ、TAKCOMと10年にわたり協業してきたアニメーションの職人。『べらぼう』の制作では、「誰もやりたがらない手間のかかる手法」を積極的に採用。浮世絵や黄表紙などのアーカイブスと実写素材を組み合わせ、妖怪の動きや炎表現まで細部に魂を込めた。1年をかけて完成に漕ぎつけた本作を「アニメーション単体でも成立する映像にできた」と振り返る。
「この映像を観て“ここで働きたい”と思ってくれる仲間が増えたら嬉しい。」
心を掴むタイトルバック、その渦はこうして生まれた!

──『べらぼう』のタイトルバックは、非常に印象的でした。まず、この映像に込められたコンセプトについて教えていただけますか?
深川:タイトルバックを担当する際、NHKでは主に内製する方法と外注する方法があります。今回は外部プロデューサーの増田さんにお願いすることになりました。
私としては渦というテーマで制作したいという想いがあって。蔦屋重三郎のウズウズであったり、江戸で暮らす人たちの疼きだったり、蔦重がみんなを巻き込んでいくエネルギーの渦、高く積み上がっていくような力を表現したかったんです。

──主人公の生き方そのものがコンセプトに繋がっているのですね。今回の映像制作におけるチームは、どのようにして編成されたのでしょうか?
増田:今回、候補に挙がっていた監督は複数いました。そのなかでも、実写からアニメーションまで幅広く対応できるTAKCOMさんが最も適任だと感じたんです。コラージュという手法を使う上で、クオリティーを担保でき、見たことのないタイトルバックを作れるだろうと。
──チームとして取り組む上で、どんな表現を目指したのでしょうか?
TAKCOM:僕たちが目指したのは、プロが見ても「これ、どうやって作ってるの?」と思えるような、境目や仕掛けが見えない映像です。普通のタイトルバックだと、「あ、この手法だな」とすぐ分かってしまう。けれど僕たちは、どこからどう動いているのか、どんな技法が使われているのか、一目では分からない。そんな精密で、まだ見たことのない映像表現に挑戦したかったんです。
石志:TAKCOMさんから「ありきたりではなく、新しい手法でできないか」と相談されたのが始まりでした。さまざまな表現手法の中で、あえて一番面倒くさい手法を選びました。誰もやってこなかったこと、やりたがらないことをあえてやろうと。
具体的には、手作業とデジタルソフトの作業を曖昧に混ぜ合わせています。どこからどこまでが手作業でどこがソフトで作ったのかのか判別できないように、印刷物のような質感、CGや3D、さらに手描きのアニメーションも組み込んでいます。
大枠のコンセプトボードの舞台裏
──コラージュという発想自体も含めて、最初はどういうところから考え始めたのでしょうか?
TAKCOM:まず深川さんのアイデアもすごく面白くて。ほかでは見たことのないような、企画として非常に独特だと感じました。
なんというか具体的なかたちになる前のウズウズしているような、エネルギーが先行している状態といいますか。すごく抽象的なワードやイメージだけが伝わってくるような印象で、それが逆にとても面白くて。そこから少しずつ、具体的なかたちに落とし込んでいった、という感じなんですね。
──最初に作られたコンセプトボードと、最終的な仕上がりとの間にはどんな違いがあったのでしょうか?
TAKCOM:コンセプトボードを共有しますね。実際に演出コンテというか、ラフな段階のものだったとしても、全体の流れやトーンなど、最終的なものとは大きくは変わっていないものです。
全体の演出は深川さんが担われていて、僕は映像監督としてタイトルバックの演出からデザイン、仕上げまでを担当しました。深川さんがしっかりフォローしてくださったので、こちらの意図をよく汲み取っていただけたと感じています。さらにある程度のストーリーは最初に共有いただいていたので、「こういう流れになるだろうな」とイメージしながら進めることができました。そこからレイアウトやデザインを練り直し、改めて組み立てていく流れでしたね。

──深川さんがすごくいいかたちでコンセプトボードのフォローや受け止めをされていたという話がありました。最初にコンセプトボードをご覧になったときには、どんな印象を受けて、どのように進めていこうと考えられたのでしょうか?
深川:コンセプトボードを見る前に、増田さんと話をしているなかでコラージュという手法を提案されました。私としては、実はコラージュに対して否定的な気持ちがありました。それが本当に心を動かすものになるのか、、自分の中で見えなかったんです。情報量が多いだけで、無機質なものになってしまうのではないかという不安がありました。
しかし、増田さんから監督をTAKCOMさんにしたいと聞きました。人を撮ってきた方だったので、人を撮る視点に期待ができると思い、考えを改めました。
その後にいただいた絵コンテで、一気に世界が広がりました。特に、女性のファインダー越しのフレーム、あのシーンには本当に心を打たれました。
そこから僕は、これを実現するために局内の調整を進めていく、この方向でいくということで、さまざまな人たちにOKを取り付けていく作業を行いました。
──今度はNHK側の調整作業もあるんですね。
深川:TAKCOMさんのやりたいこと、増田さん、石志さんのやりたいことを、しっかり形にしていく。それが僕の役割です。
コンセプトの実現のために泥臭く素材を集め、面倒な表現を技術力でカバー
──コラージュに使用する浮世絵も、非常に細部にまでこだわって集められたと伺いました。
増田:そうですね。著作権がクリアな浮世絵などから探し出しました。実際にカメラで撮ったものと、探し出した浮世絵や黄表紙をコラージュで融合させています。
石志:炎の表現はちぎり絵のように見えますが、実際の浮世絵や黄表紙を撮影し、加工しています。


TAKCOM:資料を集める段階からかなりの労力でしたね。一つひとつ切って、繋げて、貼り合わせて、一つの絵として仕上げていく。着物の素材も江戸時代の着物を保管しているところを探し、(当時の)リアルな着物を撮影してましたよね?


増田:意外と資料が少なくて、探すのに苦労しましたね。布の素材はすべて撮影したものを、石志さんのチームでちぎって加工してもらったんです。浮世絵や黄表紙については、深川ディレクターの方針で蔦屋重三郎が関わったあるいは関連した作家の作品しか使わない、という選定基準がありました。京都まで行って職人の手元を撮影したりもしています。

──タイトルバックを改めて見ると、展開がとても速く、一気に引き込まれる印象でした。視聴者も同じように感じると思うのですが、この構成にはどんな意図があったのでしょうか?
増田:たしかタイトルバックに表示する番組の登場人物の数が過去最大レベルだったんですよね。とにかく文字の量も多く、画面の遷移も早くて、これは視聴者のみなさんがついていけなくなるのでは?という懸念も一度あったんです。そのため、製作当初はもっとおとなしい構成だった時期もありました。そこから、いや、もう思い切ってやっちゃいましょう、という流れになったという経緯だったと思います。
──そこから、「もっと動きのあるものにしていこう」と、みんなで意思統一していった背景には、どういう考え方や意志があったのでしょうか?
増田:そもそも「演者、スタッフ名を出すパート」という認識ですが、「おとなしくやりすぎると物足りないかも」という深川さんの意見を受けて、挑戦的な方向に舵を切ったんです。ただ、やりすぎると読みづらくなる。そこで、展開するスピードを調整しながら、最終的なバランスを探っていきました。
──実際にアニメーションを担当されたTAKCOMさんや石志さんは、どんな工夫を?
石志:最初は紙芝居のように一枚の絵をテンポよく見せる構成を考えていましたが、それでは単調になる。逆に動かしすぎると文字が読めない。そのさじ加減をずっと模索していました。
増田:ただ、コラージュ的な手法だったり、2Dの線画と3Dアニメーションを組み合わせたりという手法が加わってきた段階で、もう少しワクワク感や楽しさを感じられる印象が必要だろうな、という話が出てきたんです。そういった意見を踏まえて、「戻れるかどうかはわからないですけど、視聴者のみなさんのワクワクにむけて挑戦してみよう」という気持ちで進めました。
カットとカットで切り替えていた部分をシームレスにつなぐようにしたり、カメラワークを入れてなめらかにしたりとTAKCOMさんや石志さんに工夫してもらって細かな調整を繰り返していきました。納品前の段階で何度も謝りながら「すみません、ちょっとだけ微調整させてください」ってお願いさせていただいて、結果的にギリギリ間に合ったという感じです。
面倒くさいことを楽しめる仲間とつくる、大河ドラマの枠を超えた挑戦
──数々の苦労を経て、この独創的なタイトルバックが完成したのですね。最後に、このチームだからこそ実現できたこと、そして作品に込めたメッセージについてお聞かせください。
増田:僕の中では、深川ディレクターと以前ご一緒した、連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』の時点で、すでに信頼関係が築けていました。だから石志さんやTAKCOMさんのちょっといきすぎた表現だと思っても、僕の方で調整するつもりでいられました。全員がのびのびと作れたのは、このチームだったからだと思います。深川ディレクターの「今までにないタイトルバックにしたい」という提案は、静的な映像が多かったこれまでの大河ドラマの枠組みにおいて、まさに挑戦でした。コラージュ、静止画アニメーション、3Dなどを駆使することで、本当に見たことのないものを表現できたと感じています。
TAKCOM:カメラマンも含め、チーム全体でアイデアを出し合いました。横浜流星さんも色々考えてくれましたね。一方通行ではなく、双方向にアイデアが行き交う、非常に有機的な現場だったと思います。ある意味、日本的とも言えるチームプレーが、この現場ではとても良い方向に作用した気がします。俺の表現をやるんだ!というようなエゴは全くありませんでしたね。全体がまとまって何かを表現したからこそ、とても良いものができたと思っています。
石志:私たちは普段からTAKCOM監督と一緒に制作しているので、自分たちができる範囲をすべて理解していただいたうえで、割と自由に制作できました。心に余裕があったと感じています。さまざまなキャッチボールができたので、それがクオリティ向上に繋がったのだと思います。
深川:完成した作品を観て感じたのは、つまり、蔦屋重三郎と今、同じ仕事をしているようなチームだったということです。蔦重はエンターテインメントの入口を作った人だと思います。誰を巻き込み、どんな物語を世の中に届けるか。例えば浮世絵ならどういう色で表現するか。蔦重がやっていたことを今、みんなでやっている。若い人たちには、「昔の話だけど、今と繋がっているんだよ」と伝わるといいなぁと思っています。XやYouTube、TikTokやInstagramなど、新しいSNSは誰もが作れるエンタメだと思います。エンタメを作る喜びを蔦重と同じように感じてもらえるきっかけになれば嬉しいですね。

▼Information
大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き 時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物 “蔦重”こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯。 笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ!
【放送予定】
[総合]日曜 午後8:00 / (再放送)翌週土曜 午後1:05
[BS]日曜 午後6:00
[BSP4K]日曜 午後0:15 / (再放送)日曜 午後6:00
写真提供:NHK